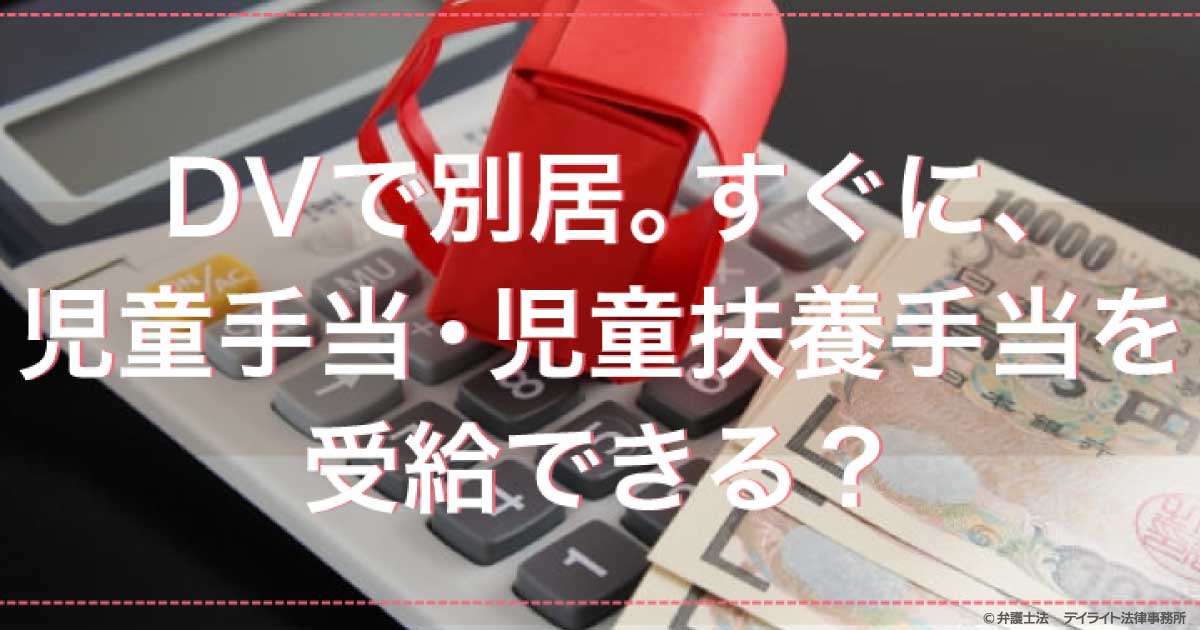シングルマザー(母子家庭)が受けられる手当|一覧表

シングルマザー(母子家庭)が受けられる手当には、児童手当、児童扶養手当、住宅手当など様々なものがあります。
どのような手当があるのか知っておくことは、現にシングルマザーである方にとってはもちろん、今後シングルマザーになる予定である方にとっても、生計維持や生活設計において非常に重要なポイントとなります。
そこで、ここではシングルマザーが受けられる手当について、一覧で紹介したうえで、特に重要な手当(児童手当、児童扶養手当、住宅手当等)について詳しく解説していきます。
なお、この記事では、配偶者との離婚・死別・未婚などの理由から単独で子ども(基本的には18歳未満)を育てている母親のことを「シングルマザー」と呼んでいます。
また、この記事で紹介する制度内容は、2025年8月現在の情報に基づいています。
目次
シングルマザー(母子家庭)が受けられる手当・助成金一覧
シングルマザーが受給・利用できる手当や助成金、制度には、主に次のようなものがあります。
| 名称 | 概要 | 窓口 |
|---|---|---|
| 児童手当 | 全ての子育て世帯に支給される手当 | 市区町村役場 |
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭に支給される手当 | 市区町村役場 |
| 特別児童扶養手当 | 精神又は身体に障害を有する子どもを育てている家庭に支給される手当 | 市区町村役場 |
| 児童育成手当 | ひとり親家庭に支給される手当 (東京都独自の制度) |
市区町村役場 |
| 生活保護 | 最低限度の生活を保障する制度 | 福祉事務所 |
| ひとり親家庭住宅手当 | ひとり親家庭に対する家賃補助等のために支給される手当 | 市区町村役場 |
| ひとり親家庭等医療費助成制度 | ひとり親家庭の親子の医療費(自己負担分)の一部を助成する制度 | 市区町村役場 |
| 乳幼児や義務教育就学児の医療費制度 | 乳幼児や義務教育就学時の医療費の一部を助成する制度 | 市区町村役場 |
| 障害児童福祉手当 | 精神又は身体に重度の障害を有する20歳未満の子どもに対して支給される手当 | 市区町村役場 |
| 就学援助制度 | 子どもの学用品・修学旅行費・給食費などの一部を支給する制度 | 教育委員会 |
| 自立支援教育訓練給付金 | シングルマザーの就業訓練のために支給されるお金 | 市区町村役場 |
| 高等職業訓練促進給付金 | シングルマザーの看護師・保育士等の資格取得を支援するために支給されるお金 | 市区町村役場 |
| 母子父子寡婦福祉貸付制度 | 就学・就職・転居資金などの目的でひとり親家庭に無利子又は低利で貸付ける制度 | 市区町村役場 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金 | 物価高騰などへの一時的な対応策として子育て世帯に対する一律給付金(内容は年度により異なる) | 市区町村役場 |
| ひとり親控除 | ひとり親が所得税・住民税の算定の基礎となる所得から一定額を控除できる制度 | 税務署(年末調整・確定申告) |
| 遺族年金 | 家計を支えていた配偶者が亡くなった場合に支給される公的年金 | 市区町村役場又は年金事務所 |
※役場の担当課については、お住いの市区町村にお問い合わせください。
※上記は一例です。自治体により制度の名称や内容は異なります。
以上のうち、児童手当、児童扶養手当、住宅手当はシングルマザーの家計の支えとして特に重要な役割を果たします。
そこで、以下では、この3つについて詳しく解説していきます。
児童手当とは?条件・期間・金額・支給日
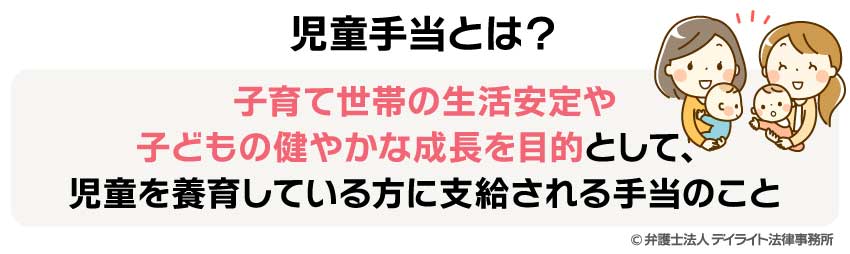
児童手当とは、子育て世帯の生活安定や子どもの健やかな成長を目的として、児童を養育している方に支給される手当のことをいいます。
全国共通の制度(国の制度)で、各市区町村が実施主体となっています。
申請等の手続きは、お住いの(住民票のある)市区町村役場で行います。
受給条件
児童手当の受給条件は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを育てている」ことです。
すなわち、高校を卒業するまでの子どもを育てている世帯であることが条件となります。
シングルマザーに限定されるものではなく、上記の年頃の子どもを育てている全ての世帯が対象となります。
子どもの父母が婚姻・同居中の場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。
離婚後は、実際に子どもと一緒に暮らして子育てをしている側が受給者となります。
離婚前であっても、離婚を前提に別居している場合や、DV被害から避難した場合などは、実際に子どもと一緒に暮らしている側が受給者となることができます。
なお、以前(2024年9月まで)は所得制限がありましたが、現在では撤廃されています。
したがって、児童手当は所得に関係なく受給することができ、所得の多少によって金額が変動することもありません。
離婚してシングルマザーになるケースでは、子どもの出生~父母の離婚までの期間は父親が受給者となっている場合が多いです。
このようなケースでは、離婚してシングルマザーとなる際、児童手当の受給者を父から母へ変更する手続きが必要となります。
具体的には、離婚日の翌日から15日以内に、父による受給事由喪失届と、母による認定請求書を提出する必要があります。
変更手続きをしないと、離婚後も父が受給者のままとなり、母が児童手当を受け取れない状況となってしまうので注意が必要です。
また、離婚前であっても、子どもを連れて別居した場合(離婚を前提に別居した場合やDVから避難した場合)は、受給者の変更申請をすることができます。
この場合には、母による申請のみで足り、父の協力は必要ありません。
ただ、その際には離婚協議中であることを証明する書類(調停の事件係属証明書など)や、DV被害を証明する書類(保護命令の決定書、相談記録など)の提出が求められます。
また、父と別居した場合は、原則として、母子が実際に住んでいる場所に住民票を異動することが求められます。
ただし、DV被害防止の観点からやむを得ない場合などは、住民票を異動しなくても受給者変更が可能です。
受給できる期間
受給できる期間は、原則として申請した月から子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
金額
児童手当の金額(月額)は、次のとおりです。
子どもの年齢や人数によって異なります。
| 子どもの年齢 | 支給額 (一人当たりの月額) |
|
|---|---|---|
| 0歳から3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
| 3歳以上高校生年代(18歳の年度末まで) | 第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
第3子以降とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どものうち、年齢が上から数えて3番目以降の子どもを指します。
18歳以上22歳未満の子どもは手当の対象にはなりませんが、大学生などで未だ独立していない場合(親に扶養されている場合)は、子どもの人数算定の際にカウントされます。
一方、18歳以上22歳未満の子どもでも、親元から独立して生計を立てている場合(親の扶養から外れている場合)は、カウント対象外となります。
例えば、子どもが19歳・17歳・10歳の3人いる場合、19歳の子どもが大学生で未だ独立していない場合は、19歳の子どもが第1子、17歳の子どもは第2子、10歳の子どもが第3子と扱われます。
一方、19歳の子どもが就職し独自に生計を立てている場合は、19歳の子どもはカウントされず、17歳の子どもが第1子、10歳の子どもが第2子と扱われます。
支給日
児童手当は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)が指定の口座に振り込まれる形で支給されます。
例えば、4月・5月分は6月に支給されます。
支給日は自治体により異なりますが、10日、15日又は20日としているところが多いです。
支給日が土日祝日に当たる場合は、通常は前営業日又は翌営業日に振り込まれます。
児童扶養手当とは?条件・期間・金額・支給日
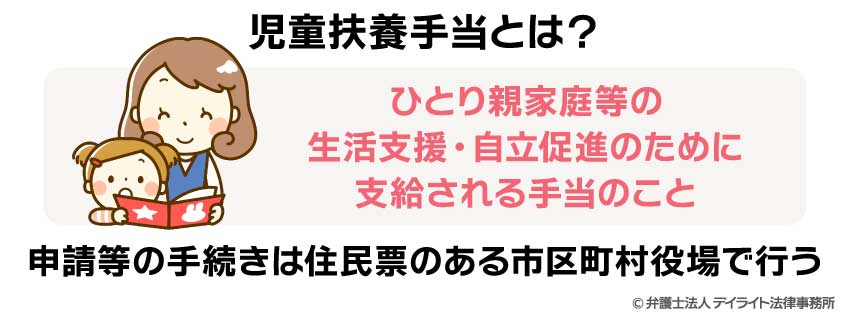
児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活支援・自立促進のために支給される手当のことをいいます。
児童手当と同じく、全国共通の制度(国の制度)で、各市区町村が実施主体となっており、申請等の手続きは住民票のある市区町村役場で行います。
受給条件
児童扶養手当の受給条件は、次のとおりです。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(一定以上の障害がある場合は20歳未満の子ども)を育てていること
- 子どもが父または母と生計を同じくしていないこと(父母が離婚・死別した場合や未婚の子など。離婚前でもDV保護命令が出ている場合などは対象となる。)
- 所得制限を満たしていること
- 内容
児童手当は全ての子育て世帯を対象にしており、所得制限もないのに対し、児童扶養手当はひとり親世帯を対象とし、所得制限が設けられています。
なお、児童扶養手当を受給するには市区町村役場での申請手続きが必要です(条件を満たしても自動的に給付されるわけではありません)。
所得制限について
児童扶養手当は、前年度の所得が一定額以上の場合、その年度の手当の全部または一部が支給停止となります。
具体的な限度額は下表のとおりです。
| 扶養人数 | 全部支給の限度額 | 一部支給の限度額 |
|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 |
| 4人目以降 | 1人増えるごとに38万円加算 | |
※所得とは、収入から法定控除額(基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除など)を差し引き養育費の8割相当を加算した額を指します。
※上記は、受給者本人の所得です。子どもの祖父母などと同居している場合は、その方の所得も考慮されます。
したがって、例えば、母親と子ども1人の母子家庭のケースでは、母親の所得が107万円を超えると一部支給となり、246万円を超えると支給停止となります。
受給期間
児童扶養手当は、原則として申請した月の翌月から子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日まで受給することができます。
子どもが一定程度以上の障害の状態にある場合は、20歳未満まで受給することができます。
障害の程度については児童扶養手当法施行令の別表第一に列挙されています。
金額(令和7年度の支給額)
児童扶養手当の金額は、全部支給の場合(全部支給の所得制限を満たす場合)は、月額46,690円(子ども1人の場合)です。
子どもが2人以上の場合は、上記の金額に子ども1人当たり11,030円が加算されます。
一部支給の場合(全部支給の所得制限は満たさないが一部支給の所得制限を満たす場合)は、月額46、680円〜11、010円(所得に応じて10円単位で異なる。子ども1人の場合。)です。
子どもが2人以上の場合は、上記の金額に11、020円~5、520円が所得に応じて加算されます。
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 子ども1人 | 46,690円 | 46,680円〜11,010円 (所得により10円単位で変動) |
| 子ども2人目以降の加算額 (1人につき) |
11,030円 | 11,020円~5,520円 (所得により10円単位で変動) |
なお、児童扶養手当の金額は、固定ではなく、物価変動に応じて毎年見直されます。
支給日
児童扶養手当は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)が指定の口座に振り込まれる形で支給されます。
例えば、3月・4月分は5月に支給されます。
支給日は自治体により異なりますが、15日としているところが多いです。
支給日が土日祝日に当たる場合は、通常は前営業日又は翌営業日に振り込まれます。
シングルマザー対象の住宅手当
シングルマザー対象の住宅手当については、全国共通ではなく、自治体ごとに制度が整備されています。
もっとも、都道府県レベルでは、公営住宅への優先入居や、就労・自立支援の一環としての住居費等の貸付け(ひとり親家庭住宅支援資金貸付)などの実質的な支援が中心となっています。
家賃補助としてお金を給付するといった直接的な支援は、一部の市区町村で独自に実施されていますが、その給付額や受給条件は様々です。
このように、住宅手当の有無や内容は地域により異なりますので、詳しくはお住いの市区町村役場でご確認ください。
以下では、主要都市における主な支援内容等について紹介いたします。
東京都の場合
東京都主体の住宅支援制度
都主体の支援としては、次のようなものがあります。
- 都営住宅への優遇抽選制度
シングルマザー家庭(ひとり親世帯)に対し、都営住宅への優遇抽選枠を設けています。都営住宅は東京都が運営する公営住宅で、家賃は民間賃貸よりも大幅に低額です。また、礼金・更新料・仲介手数料なしで入居することができます(他の府営住宅・県営住宅も同様)。 - ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(住宅支援資金)
自立支援プログラムの策定を受けたシングルマザーの方に対し、無利子で家賃の実費の貸付けをする制度です(月額上限4万円、最大12か月まで)。形式上は返還を前提とした貸付制度ですが、就職などの条件を満たせば返還免除を受けることができます。
市区町村による支援
東京都には、家賃補助等の直接給付の制度を独自に整備している市区町村が複数あります。
例えば、次のようなものがあります。
- 千代田区‥‥住居安定支援家賃助成
一定の条件を満たすひとり親世帯に対し、家賃の一部(上限5万円)、転居一時金、更新料、火災保険料の助成 - 練馬区‥‥ひとり親家庭転宅支援給付金
一定の条件を満たすひとり親世帯に対し、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料、鍵交換費用、原状回復費用、引越し費用を助成(上限40万円) - 国立市‥‥ひとり親家庭住宅費助成
一定の条件を満たすひとり親世帯に対し、ひとり親家庭に対し、住宅費の一部(月額の3分の1、上限1万円)を助成
大阪府の場合
府主体の支援として、次のようなものがあります。
- 府営住宅への優先応募枠の設定
シングルマザー家庭については、一般世帯とは別枠で応募枠を設けています。 - ひとり親家庭住宅支援資金貸付制度
自立支援プログラムの策定を受けたシングルマザーの方に対し、無利子で家賃の実費の貸付けをする制度です(月額上限7万円、最大12か月まで)。就職などの条件を満たせば返還免除を受けることができます。※政令市の大阪市、堺市では市が実施主体となります。 - 住宅確保給付金
離職や収入の減少に直面し生活が困窮している方に対し、就労支援の一環として一定の期間、家賃補助をする制度です。
※住宅確保給付金は国の制度で実施主体は主に市区町村ですが、府の福祉事務所が所管する町村では府が実施主体となります。
なお、府内の各市区町村では、市営住宅への優先入居や住居資金の貸付が支援の中心とされており、市区町村が独自に住宅手当の制度を整備している例はほとんど見られません。
福岡県の場合
県主体の支援としては、次のようなものがあります。
- 県営住宅への優先入居枠の設定
- ひとり親家庭住宅支援資金貸付制度
自立支援プログラムの策定を受けたシングルマザーの方に対し、無利子で家賃の実費の貸付けをする制度です(月額上限7万円、最大12か月まで)。
就職などの条件を満たせば返還免除を受けることができます。
※政令市の福岡市・北九州市では市が実施主体となります。
市区町村による支援
住宅手当の制度を独自に整備している例はわずかですが、次のようなものが挙げられます。
- 福岡市‥‥子育て世帯住替え助成事業
子育て世帯を対象に市外からの転居又は市内での住み替えにかかる費用を助成(上限15万円、親世帯と同居・近居、子ども2人以上の世帯は上限5万円引き上げ)
愛知県の場合
県主体の支援として、次のようなものがあります。
- 県営住宅への優先入居枠の設定
- ひとり親家庭住宅支援資金貸付制度
自立支援プログラムの策定を受けたシングルマザーの方に対し、無利子で家賃の実費の貸付けをする制度です(月額上限7万円、最大12か月まで)。
就職などの条件を満たせば返還免除を受けることができます。
※政令市の名古屋市では市が実施主体となります。
参考:愛知県ホームページ|ひとり親家庭等に対する各種支援制度
神奈川県の場合
県主体の支援としては、次のようなものがあります。
- 県営住宅への当選率優遇
- ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業
自立支援プログラムの策定を受けたシングルマザーの方に対し、無利子で家賃の実費の貸付けをする制度です(月額上限4万円、最大12か月まで)。
就職などの条件を満たせば返還免除を受けることができます。
※政令市の横浜市・川崎市・相模原市では市が実施主体となります。
市区町村による支援
神奈川県では次の市区町村で給付型の支援が実施されています。
- 鎌倉市‥‥ひとり親家庭等家賃助成制度
一定の条件を満たすひとり親世帯に対し、家賃の一部を助成(上限9,000円) - 厚木市‥‥母子家庭等家賃助成
一定の条件を満たすひとり親世帯に対し、家賃の月額に応じて一定額を助成(上限1万円) - 海老名市‥‥ひとり親家庭等家賃助成
一定の条件を満たすひとり親世帯に対し、家賃の一部を助成(一律7,000円)
シングルマザーの手当のよくあるQ&A
![]()
シングルマザー手当の総額はいくら?
児童手当や児童扶養手当は子どもの年齢や数に応じて支給されます。
また、児童手当以外のほとんどの手当てについては、所得制限が設けられています。
さらに、自治体によって制度設計や運用は異なります。
そのため、シングルマザーでも人によって受け取れる手当の総額は大きく異なります。
東京都在住のシングルマザー(子ども1人、中学生)
所得:80万円(収入ベースではおおよそ150万円)
上記のケースでは、手当(月額)はおおよそ次のようになります。
- 児童手当:10,000円
- 児童扶養手当:46,690円
- 児童育成手当:13,500円
総計:70,190円
※これ以外にも医療費の助成や家賃補助(市区町村による)等も受けることができます
大阪府在住のシングルマザー(子ども2人、小学生・中学生)
所得:300万円(収入ベースでおおよそ450万円)←所得制限超
上記のケースでは、手当(月額)はおおよそ次のようになります。
- 児童手当:20,000円(10,000円 + 10,000円)
総計:20,000円
このように、手当の総額は人によって異なるため、詳しくはお住いの市区町村役場でご確認ください。
![]()
シングルマザーは手当をもらいすぎですか?
しかし、シングルマザーへの手当は最低限の生活を保障するレベルにとどまるのが実情といわれています。
所得が低い方は、居住地によっては10万円近い手当を受け取ることができますが、それで母子家庭の生活を支えるのは難しい・ギリギリである場合がほとんどです。
また、児童手当以外のほとんどの手当には所得制限が設けられており、この制限をわずかに超えるために手当をもらうことができずに生活が厳しくなってしまうケースもあります。
まとめ
以上、シングルマザーが受けられる手当について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
児童手当は全ての子育て世帯に支給される手当ですから、確実に受給するようにしましょう。
児童扶養手当も全国共通の制度であり、所得が一定基準以下であれば受け取ることができます。
条件を満たす場合は必ず申請して確実に受給するようにしましょう。
住宅手当その他の手当・助成金については自治体ごとに異なりますので、お住いの市区町村に確認されるようにしてください。
なお、この記事では経済的支援に焦点を当てましたが、各自治体ではホームヘルプサービスや育児相談などの生活支援・心理的支援も実施されています。
これらの支援も併せて活用していくとよいでしょう。
また、養育費の請求や、離婚に伴う財産分与・慰謝料など問題については、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
これらを適切に解決することは、子育て費用の確保という点でも非常に重要なポイントとなります。
当事務所の家事事件チームに所属する弁護士はファイナンシャル・プランナーの資格を取得しており公的扶助に関する知識も豊富です。
子育てや収入にお困りのシングルマザーの方や、離婚後の生活が不安な方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?