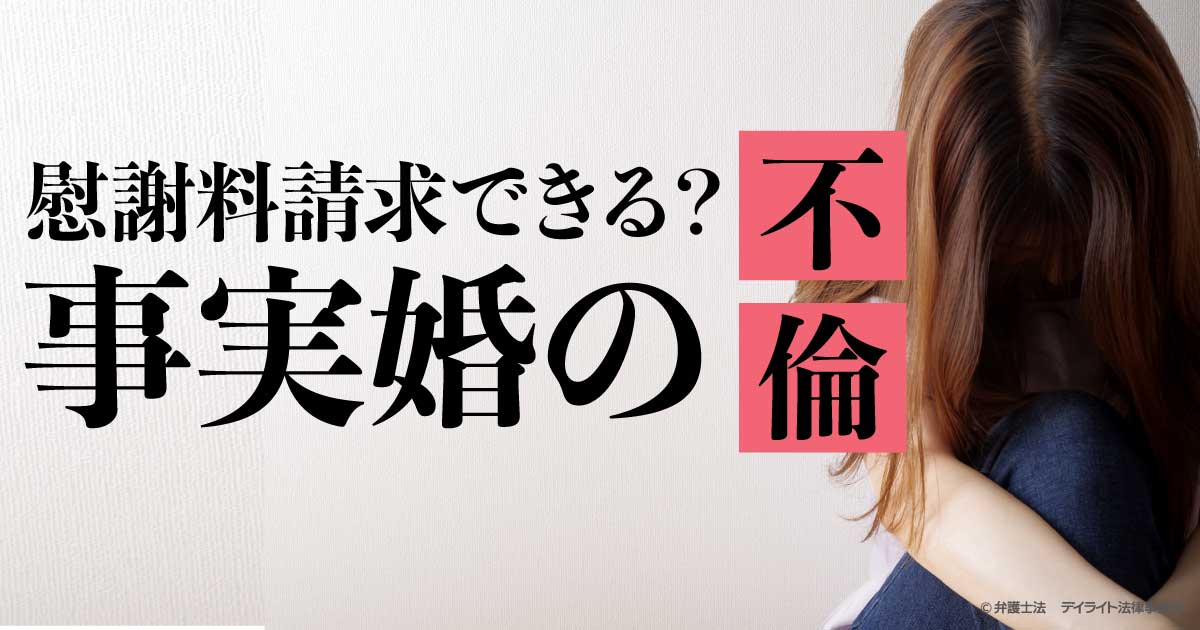事実婚のメリットとは?なぜ結婚しないのかを解説

事実婚のメリットには、次のようなものがあります。
- 夫婦別姓を維持できる(名字を変更しなくてよい)
- 戸籍の記載が変わらない
- 家のしきたりに縛られない
- 法律婚と同様の法的保護が認められる場合もある
近年では、結婚に伴う名字・戸籍の変更や、「家に入る」といった家制度的な慣習に縛られることに対して違和感を覚える方も多くなってきています。
そのため、上記のようなメリットがある事実婚に注目する方も増えているようです。
そこで、ここでは事実婚のメリットを中心に、事実婚を選ぶ理由、事実婚のデメリットなどについても解説していきます。
事実婚のメリットとは?
事実婚とは、双方が夫婦として生活する意思を持ち、夫婦としての生活実態もあるものの、婚姻届を出しておらず法律上の夫婦とは認められない男女の関係のことをいいます。
事実婚には次のようなメリットがあります。
| 事実婚のメリット |
|---|
|
-
夫婦別姓を維持できる(名字を変更しなくてよい)
婚姻届を出す場合(法律婚の場合)は、夫婦は同一の氏(姓・名字)を名乗る必要があります。
そのため、夫婦のどちらかが改姓(名字の変更)を迫られることになります。
一方、事実婚の場合は夫婦同姓の制約を受けず、夫婦がそれぞれ自分の名字を名乗り続けることができます。
そのため、改姓に伴う負担や影響を避けることができます。
改姓に伴う負担や影響としては、以下のようなものが挙げられます。
- 運転免許証、旅券、銀行口座、クレジットカード等あらゆる証明書や契約の名義変更が必要となる
- 仕事上の混乱や不都合を招くことがある
- 私生活を知られるきっかけとなる(「結婚したの?」と聞かれるなど)
- 自己喪失感につながる
- 「〇〇家に入る」という家制度的な意味付けをされることがある
- 夫婦の一方のみ(女性が圧倒的に多い)が改姓を強いられるため、男女の対等性が損なわれる可能性がある
このように、改姓による負担や影響は、手続的・事務的なものにとどまらず、社会的・心理的なものにまで及ぶことがあります。
戸籍の記載が変わらない
婚姻届を出すと、夫婦は同一の戸籍に記載されることになります。
多くのケースでは、夫を筆頭者とする戸籍が新たに編成されるか、夫の戸籍に妻が入る(入籍する)形をとることになります。
また、戸籍に「婚姻」の記録が残ることになります。
一方、事実婚の場合は、このような戸籍の変動はありません。
夫婦で別々の戸籍を維持することができ、「婚姻」の記録も残りません(万一別れても「離婚」の記録は残りません)。
これは、戸籍制度に違和感を持つ方や、戸籍に結婚歴・離婚歴を残したくない方にとっては大きなメリットとなります。
家のしきたりに縛られない
法律婚の場合は、結婚した途端に「嫁」「婿」と扱われ、「〇〇家の一員」として振る舞うことを期待されてしまうことが多いです。
これは、法律婚に伴う夫婦同姓や同一戸籍に深く関わるものと考えられます。
結婚して名字や戸籍が一緒になることは、戦前の家制度の「結婚=家に入る=戸主に従う」という構造とイメージが重なるためです。
そのため、結婚すると親族などから「〇〇家の一員」と認識され、その家のしきたりに従うことを求められてしまうことが多いです。
一方、事実婚の場合は、結婚をしても夫婦同姓や同一戸籍を避けることができるため、「〇〇家の一員」と認識されることも避けやすくなります。
そのため、家のしきたりに従うことや、親戚づきあいを期待されることからも自由でいられることが多いです。
法律婚と同様の法的保護が認められる場合もある
事実婚の夫婦には法律上の夫婦関係は認められません。
しかし、事実婚は「法律婚に準じた関係」と考えられているため、事実婚のパートナーは一定の法的保護を受けることができます。
例えば、民法上の、夫婦の扶助義務、生活費の分担義務、貞操義務、関係解消時の財産分与などに関する規定は、事実婚にも適用されると考えられています。
そのため、例えば、事実婚の夫婦の一方が浮気をした場合、他方は浮気をした側に慰謝料を法的に請求することができます。
事実婚で税金が安くなる?
事実婚のパートナーは税制上の「配偶者」には該当しないと考えられています。
そのため、配偶者としての税制上の優遇(所得税の配偶者控除、相続税の減税措置など)は受けることができません。
したがって、事実婚であることを理由に税金が安くなることは基本的にはありません。
税金面においては、法律婚と比べると、事実婚の方が不利になることが多いです。
一方、健康保険や厚生年金などの社会保険においては、事実婚の場合でも法律婚と同様の扱いを受けることができます。
そのため、条件を満たせば事実婚のパートナーでも社会保険の扶養に入ることができます。
したがって、事実婚で社会保険料を抑えられる(扶養に入った人自身は保険料を払わなくて済み、世帯としての保険料を抑えられる)ケースはあります。
なぜ結婚しないの?事実婚を選択する人の声
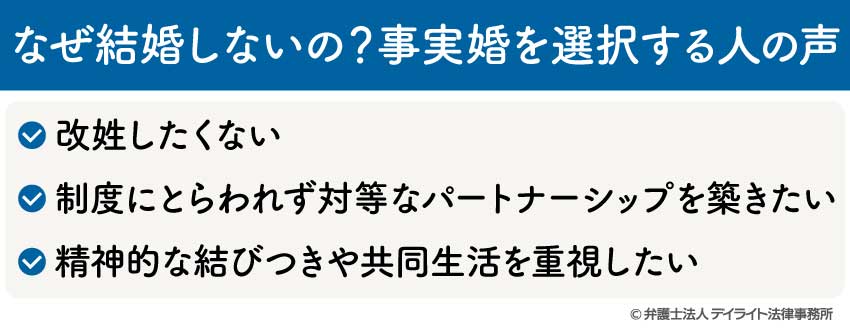
改姓したくない
事実婚を選択する理由として最も多いのは、「夫婦別姓を通すため」だそうです。
参考:内閣府男女共同参画局「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」(2021年11月30日)資料3
先に述べたように、改姓には様々な負担や影響が伴います。
そのため、「結婚したいけれども改姓はしたくない」という方(特に女性)は多いです。
そして、改姓せずに結婚する方法として、事実婚が選択されることになります。
中には、法律婚を望みつつも、改姓が障害となるため、法律婚を「諦めて」事実婚を選択するケースもあります。
制度にとらわれず対等なパートナーシップを築きたい
価値観の多様化が進む現代では、男女を問わず、夫婦同姓や戸籍制度に違和感を覚える方は増えてきています。
このような違和感を排除し、対等なパートナーシップを築くことを望んで事実婚を選択する方もいらっしゃいます。
精神的な結びつきや共同生活を重視したい
法制度上は「結婚=婚姻届の提出」と定義されますが、本来の「結婚」という言葉の意味はもっと広く多様であり、人によっても考えが異なります。
そして、事実婚を選択する人の多くは、相手との精神的な結びつきや共同生活を重視し、これを「結婚」と考えて実践しています。
したがって、事実婚の選択は「結婚しない選択」なのではなく、「自分たちなりの結婚を実践するための選択」であると考えることもできます。
事実婚のデメリットとは?
事実婚には次のようなデメリットもあります。
| 事実婚のデメリット |
|---|
|
-
法定相続人としての権利がない
法律婚の「配偶者」は、常に法定相続人(法律上相続する権利を持つ人)になることができます。
そのため、相手が先に亡くなった場合は、相手の遺産を相続によって承継することができます。
一方、事実婚のパートナーは法定相続人としての権利はありません。
そのため、相手が先に亡くなった場合、当然には遺産を承継することができません。
事実婚のパートナーが遺産を引き継げるようにするためには、事前の対策が必要となります。
例えば、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の活用などが考えられます。
ただ、このような対策によって遺産を承継できる場合でも、税金面等では法律婚よりも不利になってしまうことが多いです。
税制上の優遇を受けることができない
先に述べたとおり、事実婚のパートナーは「配偶者」として税制上の優遇を受けることができません。
そのため、法律婚と比べると、事実婚の方が税金面では不利になることが多いです。
法律上の父子関係の確保には認知が必要
法律婚の場合は、父親と子どもの法律上の親子関係は当然に成立します。
一方、事実婚の場合は、父親と子どもの法律上の親子関係は当然には成立しません。
父親との法律上の親子関係を成立させるためには、父親による「認知」が必要となります。
認知をしないままでいると、子どもが父親を相続する権利や、父親に扶養を求める権利も発生しないままとなってしまいます。
また、認知をした場合であっても、子どもの親権を持つのは原則として母親のみです。
父親も親権を持つためには、別途手続き(届出※)が必要となります。
(※)以前は事実婚の場合は父母の一方のみが親権者となるとされていましたが、法律改正により、事実婚でも届出により父母が共同で親権者となることが可能となりました(2026年5月施行)。
医療行為の同意などができない場合がある
事実婚の場合、医療や介護などの現場で「家族」として扱ってもらえず、医療行為の同意等ができないことがあります。
施設によって運用は異なりますが、法律上の関係性の有無によって区別がされてしまうケースも少なくありません。
事実婚のメリットについてのQ&A
![]()
事実婚の子どもはどうなるの?
認知をして初めて子どもの相続権や父親に扶養を求める権利も発生します。
なお、認知をしても、子どもの親権者は原則母親のみとなります。
父親も親権者とするためには別途手続きが必要です。
また、子どもは原則として母親の戸籍に入るため、子どもは母親の名字を名乗ることになります。
子どもに父親の名字を名乗らせたい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てる必要があります。
![]()
事実婚は別れやすい夫婦ですか?
しかし、相手の同意を得ずに一方的に関係解消(家を出て消息を絶つなど)をすると、慰謝料請求という形で責任追及をされる可能性があります。
また、合意によって関係解消する場合でも、法律婚の夫婦が離婚をする場合と同じように、財産分与や子どもの親権・養育費などをめぐって対立が生じるケースがあります。
そのため、事実婚だからといって別れるのが簡単とは限りません。
まとめ
以上、事実婚のメリットについて解説しました。
事実婚には、名字や戸籍を変更せずに夫婦として生活することができ、一定の法的保護も受けられるといったメリットがあります。
結婚しても名字や戸籍を変えたくない人や、家制度的な関係性から距離を置きたい人にとっては、事実婚は魅力的な選択肢となるかもしれません。
一方、事実婚には、相続、税金、父子関係、医療同意などの面で不安定・不利益な立場になる可能性があるといったデメリットもあります。
事実婚を考える場合は、これらのデメリットにも注意して、対策を講じることが大切です。
必要に応じて男女問題・離婚問題に詳しい弁護士への相談もおすすめいたします。
当事務所には、男女問題や離婚問題に専門特化したチームがあり、夫婦関係の問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており全国対応が可能です。
お悩みの方は気軽にご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?