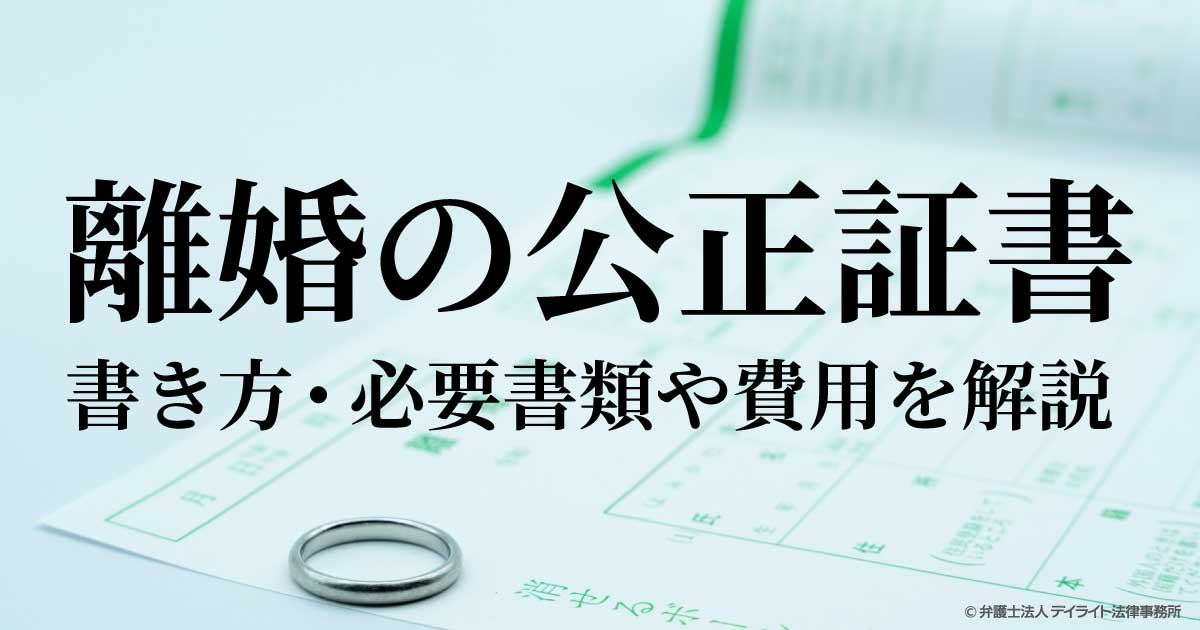面会交流の取り決め例|弁護士がケース別の条項例を紹介

夫婦が離婚する際に、面会交流についての取り決めがなされることが多いですが、どのような内容の取り決めをするべきかはケース・バイ・ケースです。
例えば、夫婦が別居して離婚の話し合いをしているが、その間も夫婦双方の協力の下、無理なく円滑で適切な面会交流が実施されている。子どもも離れて暮らしている親と会う機会をとても楽しみにしている。
こうした状況下での面会交流の取り決めは、事細かにするまでの必要はないと思われます。
しかし、こうしたケースは決して多いとはいえません。
離婚に際しては、夫婦の感情的対立が激化しているため、同居親はできる限り面会交流をさせたくない、別居親はできる限り面会交流をしたいと考えがちです。
そのため、後々のトラブル防止のために、できる限り細かい取り決めをする必要があるケースが多く見られます。
ここでは、様々なケースの面会交流の条項例を紹介しています。
また、面会交流の取り決めの注意点についても、面会交流に精通した弁護士が解説しています。
ぜひ参考になさってください。
※このページで掲載している面会交流の条項の使用は、面会交流に苦しむ当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。
他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりません。
面会交流の取り決め内容で押さえておくべき要素

面会交流の取り決め内容には、大きく分けて、頻度、日時、方法があります。
①頻度
頻度とは、別居親と子どもが面会交流をする回数を月何回にするかなどです。
例えば、月に1回とすることが適切な場合もあれば、月2回とすることが適切な場合もあります。
何が適切かは、子どもの年齢、意思その他様々な事情から検討していくことになります。
②日程
面会交流の日時については、例えば、毎月第○土曜日の○○時~○○時という取り決めがあります。
日時を細かく取り決める必要があるか、あるとしてどのような内容とするのが適切かは、子どもの年齢、意思その他様々な事情から検討していくことになります。
③方法
方法とは、面会交流をどうやって実施するかという問題です。
例えば、宿泊付きの面会交流を認めるのか、学校行事への参加を認めるのか、手紙でのやり取りを認めるのか等があります。
これについても、様々な事情から検討していくことになります。
面会交流の取り決め例

以下では、面会交流の具体的な条項例を紹介します。
なお、ここで紹介する条項例は、当事務所の離婚事件部に所属する弁護士が執筆した次の書籍の一部を抜粋したものです。
書籍情報:「離婚協議書・婚姻契約条項例集―面会交流・養育費・財産分与・婚姻費用・年金分割、パートナーシップ契約等」(日本加除出版株式会社)
一般的な取り決めの例
乙は、甲に対し、甲が未成年者と月1回程度、面会交流することを認め、その具体的な時間、場所、方法等については、子の利益を最優先に考慮し、当事者間で協議して定める。
※「甲」を別居親、「乙」を同居親として記載しています。
この条項例は、別居している夫婦において、すでに面会交流を実施している、あるいは今後面会交流をすることが可能な事案において、もっともシンプルな取り決めです。
頻度を定める場合、上の例のように「月1回程度」などと定めることが多いです。
月2回の場合は「月2回程度」、週1回程度の場合は「週1回程度」などと記載します。
面会交流において対立関係が生じる場合は、①面会交流の頻度のほか、②時間、場所、方法等の決め方、③事前協議の方法についても細かく定めておく必要が生じますが、そういった必要性が低い事案の場合は、上記条項例とすることが一般的です。
なお、面会交流が全く問題ない状況(父子の関係が良好で、父母の関係も問題がない事案など)では、具体的な頻度すら定めないケースもあります。
その場合、下記のように記載すればよいでしょう。
宿泊を伴う面会交流の取り決め例
乙は、甲に対し、未成年者が春休みや夏休み等長期休暇期間中に、甲が未成年者と、1泊2日の宿泊を伴う面会交流することを認める。
その具体的な時間、場所、方法等については、子の利益を最優先に考慮し、当事者間で協議して定める。
この条項例は、月1回程度の面会交流を実施することの他、子の長期休暇中においては宿泊を伴う面会交流の実施を合意したケースの例です。
「長期休暇」は、春休みや夏休みの他、年末年始はどうなのか、ゴールデンウィーク期間はどうなのか、お盆休みはどうなのか、といった議論がなされる場合もあります。
プレゼントを認める場合の取り決め例
乙は、甲に対し、未成年者の誕生日、クリスマス、進級等の特別な機会にプレゼントを渡すことを認める。
(対立関係が強い場合)
- (1) 乙は、甲に対し、未成年者の誕生日、クリスマス、進級等の特別な機会にプレゼントを渡すことを妨げない。
- (2) プレゼントの価額は、⚫⚫円までとする。
この条項例は、非監護親が子に対し、プレゼントを渡す際の取り決めのサンプルです。
別居親の親族が同席する場合の取り決め例
乙は、甲に対し、甲の祖父丙が、前項の面会交流の際、未成年者に会うことを認める。
(親族の交流回数を制限する場合)
乙は、甲に対し、甲の祖父丙が、年2回、面会交流の際に未成年者に会うことができる。
(親族の同席は認めるが、それ以外の第三者の同席を認めない場合)
甲は、乙の承諾なく甲以外の第三者(甲の親族を除く。)を同席させない。
(非監護親に都度の承諾を求める場合)
甲は、乙の承諾なく、甲の親族を面会交流に同席させない。
(対立関係が強い場合)
甲は、乙の承諾なく、年に2回を超えて、甲の親族を同席させない。
この条項例は、親族が面会交流に同席するケースを想定したものです。
未成年者が幼児の場合の取り決め例
1 乙は、甲に対し、甲が未成年者と月1回程度、面会交流することを認め、その具体的な時間、場所、方法等については、子の利益を最優先に考慮し、当事者間で協議して定める。
2 甲及び乙は、未成年者の面会交流について、以下のとおり相互に確認する。
(1) 甲は、面会交流中に未成年者と食事をとる場合、未成年者の成長に合わせた適切な食事を与えることとする。
(2) 甲は、面会交流の内容(行先、食事等)について、前日までに乙に伝える。
(3) 甲は、面会交流中、未成年者の言動にかかわらず、定期的にトイレに連れて行くようにする。
この条項例は、未成年者が幼児で、食事やトイレなどを十分に一人でできない場合の注意事項を明記したものです。
学校行事への参加の取り決め例
1 乙は、甲に対し、甲が未成年者と月1回程度、面会交流することを認め、その具体的な時間、場所、方法等については、子の利益を最優先に考慮し、当事者間で協議して定める。
2 (1) 乙は、甲が、未成年者の参観日や学校行事等(以下「行事等」という。)に参加することを認める。
(2) 行事等への参加は1回の面会交流と数え、行事等について、甲が参加する場合は乙が参加を控え、乙が参加する場合は甲が参加を控える。
学校行事などへの参加に関する取り決めも、面会交流の一環として協議されることが多くあります。
この条項例は、非監護親が参加する場合のサンプルとなります。
間接的面会(手紙と写真の送付)の取り決め例
(1) 乙は、甲に対し、甲が未成年者に手紙を送付することを認め、これを妨げない。
(2) 乙は、甲に対し、●か月に1回程度、上記未成年者の写真を送付するとともに、同人の近況報告の
手紙を送付する。
本取り決めは、直接の面会交流を実施することが困難な状況において、間接的面会交流を継続する場合の例です。
何らかの理由で子が非監護親に対して消極的なイメージを持っている場合、あるいはその感情が強固な場合、直接の面会交流が実現できない場合があります。
こういったケースでは、非監護親側が粘り強く子への関心を発信し続け、子がそれに応えてくれることを待たざるを得ない状況がしばしばあります。
第三者機関を使う場合の取り決め例
1 乙は、甲に対し、甲が未成年者と面会交流することを認め、その具体的な時間、場所、方法等については、子の利益を最優先に考慮し、当事者間で協議して定める。
2 前項の面会交流においては、第三者機関(●●●)の受渡型サポートを利用するものとし、それに要する費用を以下のとおり負担する。
(1)1回あたりの利用料金については、甲3分の1、乙3分の2の割合でそれぞれ負担する。ただし、100円未満の端数については、申立人が負担する。
(2)年会費については、当事者双方がそれぞれ負担する。
(3)受渡後の交通費、飲食費及び施設利用料等の実費については、甲がいずれも負担する。
この条項例は、同居親と別居親が面会交流について、第三者機関を利用する合意ができた場合のサンプルです。
第三者機関とは、面会交流に関する支援を行っている団体で、全国にありますが、存在しない都道府県もあります。
面会交流の強制執行(間接強制)を想定した場合の取り決め例
(1)面会交流の日時については、毎月第2土曜日の午前10時から午後5時までとする。
(2)面会交流の場所は、乙の自宅以外の甲が定めた場所とする。
(3)未成年者の引き渡しの方法は、面会交流開始時に、JR◯◯駅◯◯改札付近において乙が甲に対し未成年者を引渡し、面会交流終了時に、JR◯◯駅◯◯改札付近において甲が乙に対し未成年者を引渡す。
この条項例は、面会交流がスムーズに実施されない可能性が高い場合に、強制執行(間接強制)を想定した場合の取り決め例です。
同居親が面会交流に応じない場合、別居親は強制執行をすることになりますが、日時・頻度、時間、子の引き渡しの方法が具体的で明確でなければ、間接強制できません。
そのため、上記条項例では、この点について明確に記載しています。
なお、間接強制については、債務名義(調停調書、審判書や判決書等)が必要となるため注意してください。
面会交流の取り決めの注意点

面会交流の取り決めの注意点について解説いたします。
ケースに応じて適切な条項を使う
このページでは、いくつかのケースにおける面会交流の条項例をご紹介しています。
しかし、最適な面会交流の条項は、当事者のおかれたご状況によって異なります。
したがって、上の条項例は参考程度とし、専門家にご相談の上、最適な条項を作成するようにしてください。
面会交流のルールとは区別する
このページでご紹介した条項例は、面会交流についての頻度、日時、方法等についての合意事項となります。
面会交流がうまくいっていないケースの場合、面会交流の条項とは別に、面会交流のルールを策定することもあります。
面会交流のルールとは、例えば、相手の悪口を子どもの前で言わない、受け渡しの時間をきちんと守る、などです。
特に、面会交流を実施してすぐは、相手への不信感などがあります。
そのため、ルールを守って、相手の安心感を得ることが重要です。
相手に安心してもらうことができれば、面会交流のさらなる充実が期待できます。
面会交流のルールについては、下記のページにてくわしく解説しています。
面会交流の強制執行は難しい
面会交流は、その性質上、直接強制(直接の実力行使による面会交流の実現)という方法に馴染みません。
面会交流の調停で決まったとおりに面会交流が実現しない場合、間接強制(面会交流させないことに対して一定の金銭の支払いを命ずるもの)という制度を使って面会交流を実現していくことになります。
面会交流についての合意を締結する際、父母の対立が激しく、面会交流の実現が難しいことが予想される場合、この間接強制に適した面会交流の条項を検討しなければなりません。
間接強制に適した条項のサンプルは、上の条項例でご紹介していますが、状況に適した内容にすべきです。
また、債務名義(調停調書など)が必要となる点にも注意が必要です。
面会交流の取り決めは専門家に相談
面会交流について、適切な合意を行うためには法的な専門知識が必要となります。
また、面会交流の条項は、一度取り決めると後々簡単に変更することはできません。
そのため、面会交流の取り決めをご検討されている方は、専門家にご相談の上、慎重に締結なさってください。
面会交流の取り決めについてのQ&A
ここでは、面会交流の取り決めに関してよくあるご質問と回答をご紹介しています。
![]()
面会交流の取り決めを守る義務はあるか?
![]() 面会交流の取り決めを行った場合、基本的には相手に対してその合意内容を守る義務があると考えられます。
面会交流の取り決めを行った場合、基本的には相手に対してその合意内容を守る義務があると考えられます。
また、合意内容を一方的に破った場合、相手が親権者変更の申立て、養育費の不払いなどの対応をとることが懸念されます。
そのため、面会交流の実施が難しいなどの状況が生じた場合、相手と協議するなどして円満に解決を図るべきです。
もし、相手との協議が難しいような状況であれば、弁護士に間に入ってもらうことを検討しましょう。
![]()
面会交流の取り決めはしなくてもいいですか?
![]() 面会交流の取り決めは法的な義務ではありません。
面会交流の取り決めは法的な義務ではありません。
しかし、お子さんがいる場合、充実した面会交流の実現やトラブルの防止の観点から、できるだけ面会交流の取り決めを行った方がよいと考えます。
ただし、取り決めの内容や方法(合意書、公正証書、調停調書など)はケース・バイ・ケースとなります。
![]()
面会交流の取り決めは公正証書にすべき?
![]() 状況にもよりますが、面会交流だけの合意であれば、公正証書にしなくて良いと考えます。
状況にもよりますが、面会交流だけの合意であれば、公正証書にしなくて良いと考えます。
例えば、養育費や慰謝料(長期分割払い)があるケースで、権利者側の場合、公正証書にするメリットがあります。
これらの合意とあわせて面会交流の取り決めをする場合、公正証書の締結をお勧めいたします。
まとめ
以上、面会交流の取り決めの具体例、取り決めの注意点について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
面会交流は父母の対立の程度、子供の年齢、父子の関係性、居住場所などの状況に照らして、最適な条項を作成することがポイントとなります。
また、父母の対立がひどい場合、面会交流の条項とは別に、面会交流のルールを策定することも検討しましょう。
面会交流を円滑に実施するためには法的な専門知識・経験が必要となります。
そのため、面会交流にくわしい専門家の助言を受け、慎重に行動するようにしましょう。
当事務所には離婚問題に注力する弁護士のみで構成される専門チームがあり、面会交流などの離婚に関する条項に精通しています。
面会交流でお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?