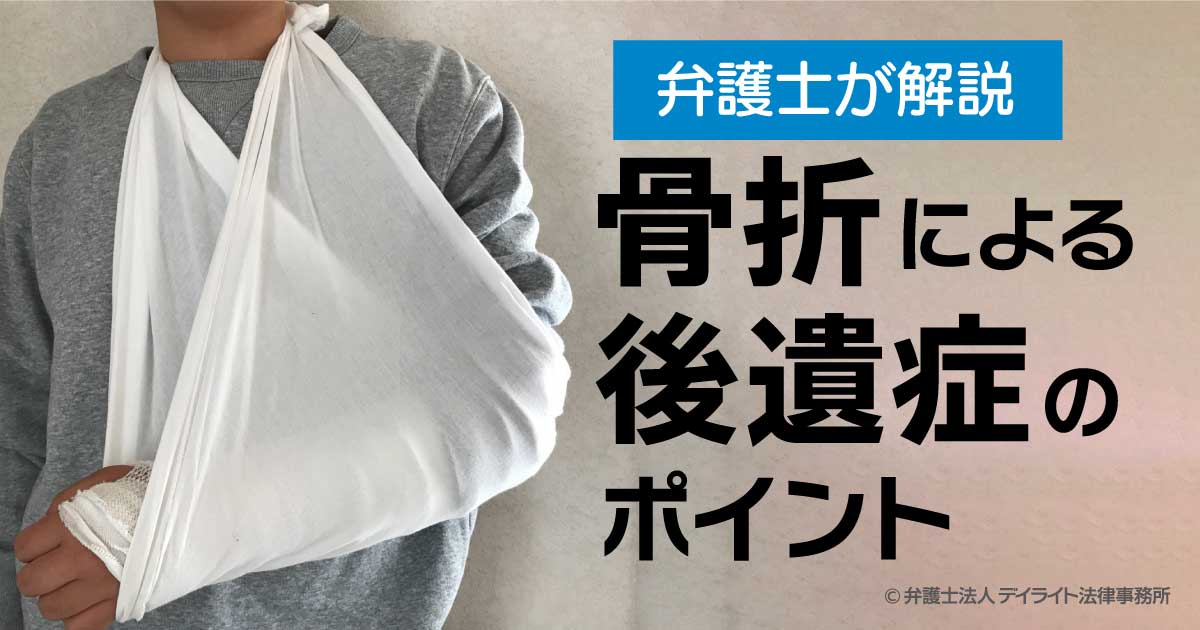可動域制限とは?原因・治療から後遺障害認定まで完全ガイド
 可動域制限(かどういきせいげん、ROM制限)とは、外傷や疾病などによって関節を動かせる範囲、すなわち関節可動域が、障害のない正常な関節と比較して狭くなっている状態を指します。
可動域制限(かどういきせいげん、ROM制限)とは、外傷や疾病などによって関節を動かせる範囲、すなわち関節可動域が、障害のない正常な関節と比較して狭くなっている状態を指します。
可動域制限は、その程度が客観的な測定値で示されるため、後遺障害として認められやすい症状です。
ただし、適正な等級認定と高額な賠償金を獲得するためには、「器質的な原因の医学的立証」と「正確な可動域の測定」が不可欠です。
この記事では、可動域制限の概要や症状や、可動域制限の原因となる具体的な損傷、可動域制限の治療法、そして受け取れる賠償金の種類などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
目次
可動域制限とは?
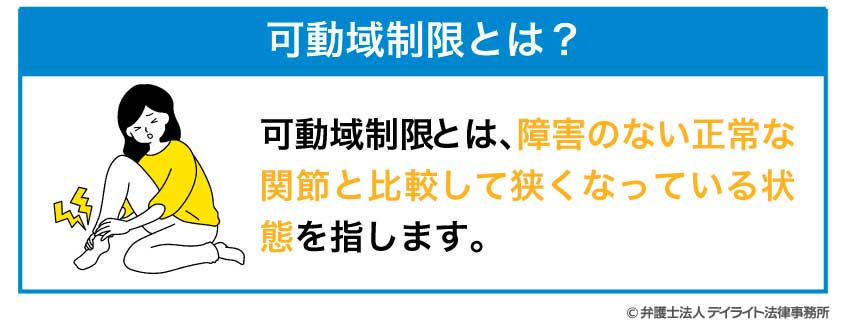
可動域制限(かどういきせいげん、ROM制限)とは、外傷や疾病などによって関節を動かせる範囲、すなわち関節可動域が、障害のない正常な関節と比較して狭くなっている状態を指します。
具体的には、負傷した関節が「曲がりにくい」、「伸びにくい」といった、動作範囲の制約が生じる状態です。
交通事故や労災事故における負傷でしばしば問題となる症状であり、その程度が重大である場合には、後遺障害の対象として多数の認定例があります。
そして、関節の可動域は、医学的な検査によって正確な測定値として示されます。
通常、この測定値は、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会が定めた測定法に基づき、分度器(角度計)を用いて計測されます。
後遺障害の等級認定においても、この測定値が極めて重要な判断要素となります。
関節の可動域が、健側(障害のない側の関節)や、厚生労働省が定める関節の標準的な可動域と比較して、どの程度制限されているかによって、後遺障害等級に該当するか否かが判定されることになります。
交通事故による後遺障害の認定では、原則として関節の他動(他人の力によって関節を動かす)の可動域を測定し、健側(可動域制限のない健康な方)の可動域と比較して制限の程度を判断します。
可動域制限の症状
可動域制限によって生じる症状は、その原因となる損傷部位や程度によって多岐にわたりますが、中心となるのは関節運動の障害とそれに伴う疼痛です。
最も直接的な症状は、特定の関節を動かそうとした際に、健常な範囲まで動かすことができないという動作の制約です。
これは、単に関節が曲がらない、伸びないといった物理的な制限に留まらず、日常生活における様々な動作に支障をきたします。
例えば、肩関節の可動域が制限された場合、高い位置の物を取ろうとする動作(挙上)や、背中に手を回す動作(結帯動作)が困難になります。
膝関節や股関節であれば、歩行時のスムーズな屈曲・伸展が妨げられ、階段の昇降や正座などが不可能になる場合があります。
また、可動域の終末域、すなわち関節を限界まで動かそうとした際に、強い痛みが伴うことも主要な症状の一つです。
この痛みは、関節包や靭帯などの軟部組織が硬くなった(拘縮した)ことによる伸張痛や、関節内の組織が挟み込まれること(インピンジメント)によって生じる炎症によるものです。
さらに、可動域制限は、その関節だけでなく、周囲の筋肉や連動する関節にも影響を及ぼします。
可動域が制限された関節をかばうために代償動作が生じ、結果として、本来負担がかからない他の部位に二次的な疼痛や障害を引き起こすことがあります。
例えば、股関節の可動域が制限されると、腰椎を過度にひねる動作で代償し、腰痛を誘発するといったケースが見られます。
これらの症状は、日常生活の質を著しく低下させ、特に労働能力の喪失にも直結するため、法的な損害賠償請求においては、後遺障害等級の認定を通じて逸失利益や後遺障害慰謝料の算定に大きく関わってきます。
医学的な検査で測定される可動域の数値は、これらの機能的・実用的な障害の客観的な証拠として機能します。
可動域制限の原因
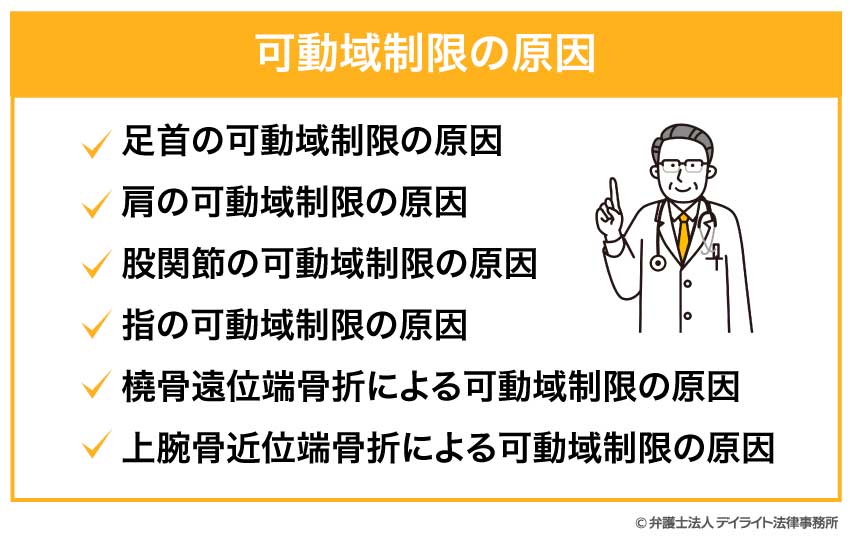
可動域制限(ROM制限)の主たる原因として、外傷によって骨、関節軟骨、関節包、靭帯、腱、筋肉といった組織に生じた器質的変化(物理的な損傷や変性)、や機能的変化(神経麻痺や疼痛による運動の抑制)を挙げることができます。
後遺障害認定を獲得するためには、単に可動域が制限されているという事実だけでなく、X線、CT、MRIなどの画像検査によって、その制限を引き起こしている器質的な原因を医学的に立証することが不可欠です。
以下に、特定の部位や外傷における可動域制限の典型的な原因を詳述します。
足首の可動域制限の原因
足首(足関節)は、脛骨(すねの太い骨)、腓骨(すねの細い骨)、距骨(かかとの上の骨)の3つの骨から構成され、特に強いねじれや圧迫力が加わる交通事故で損傷しやすい部位です。
足関節の可動域制限の原因となる傷病として、以下のようなものがあります。
- 足関節果部骨折・脛骨天蓋骨折(ピロン骨折):くるぶし(内果・外果)や脛骨の関節面に近い部分(脛骨天蓋)の骨折は、関節面の不適合や変形を招き、背屈(足首を甲側に上げる)や底屈(足首を足の裏側に下げる)の動きを制限します。
- 靭帯損傷・脱臼:重度の捻挫(前距腓靭帯損傷など)や脱臼に伴い、関節包や靭帯が損傷・修復される過程で線維化し、関節の安定性と可動性を低下させます。
なお、足関節の外傷の原因と傷病名や、後遺障害等級、可動域の計測方法などについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。
肩の可動域制限の原因
肩関節(上腕骨・肩甲骨・鎖骨からなる複合体)は、体で最も可動範囲が広い関節であり、制限が生じた場合の機能的障害は甚大です。
肩関節の可動域が制限される傷病として、以下のものがあります。
- 上腕骨近位端骨折:肩関節に近い部分の骨折であり、骨片が転位(ズレ)すると、肩を動かす筋肉(特に腱板)の付着部に影響を及ぼし、挙上、外転、外旋などの主要な運動を大幅に制限します。
適切な整復が行われないと、不正癒合による変形によって可動域制限が残る可能性があります。 - 肩腱板断裂:腱板(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋の腱)の断裂は、自力で腕を上げる力(自動運動)を低下させるだけでなく、断裂に伴う炎症や瘢痕形成が関節包に波及し、関節包性拘縮を引き起こして他動的な可動域も制限することがあります。
- 肩鎖関節脱臼:鎖骨と肩甲骨をつなぐ関節の脱臼では、靭帯損傷後の不安定性や変形が、間接的に肩関節全体の動きに制限をもたらすことがあります。
なお、肩関節の可動域制限の後遺障害や、肩関節の可動域の測定方法、賠償例などについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。
股関節の可動域制限の原因
股関節は深いくぼみ(臼蓋)に大腿骨頭がはまり込んでいるため安定性が高い反面、一度損傷すると重篤な可動域制限を残しやすい関節です。
交通事故によって股関節の可動域が制限される原因として、以下のような傷病が挙げられます。
- 大腿骨頸部骨折・転子部骨折・股関節脱臼骨折:大腿骨の近位部(股関節側)の骨折や脱臼は、股関節の適合性を根本から損ないます。
屈曲、内旋、外旋といった全ての運動が制限され、重度の場合は人工関節置換術が必要となることがあります。 - 変形性股関節症への進行:骨折や脱臼後の関節軟骨の損傷から、二次性の変形性股関節症へ移行することで、関節の破壊が進み、不可逆的な可動域制限が生じます。
なお、股関節の可動域が制限された場合の後遺障害等級や、股関節の可動域の計測方法などについて以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。
指の可動域制限の原因
指の関節(中手指節関節・指節間関節)の可動域制限は、日常生活動作に直接的な影響を及ぼします。
交通事故によって指の関節の可動域が制限される原因として、以下のような傷病が挙げられます。
- 腱の損傷・癒着:交通事故で指を強く打撲・切創した場合、指の動きを司る屈筋腱や伸筋腱が損傷したり、周囲の腱鞘や骨に癒着したりすることで、指の屈曲(曲げる)や伸展(伸ばす)が阻害されます(器質的変化)。
- 指骨・中手骨の骨折:骨折後の不整な癒合や、固定による関節の拘縮(関節自体の強直を含む)が、器質的な制限となります。
- 神経麻痺:正中神経、尺骨神経、橈骨神経などの麻痺により、特定の筋肉が機能しなくなり、自力での指の操作(機能的変化)が困難になることがあります。
- 骨折による可動域制限の原因
骨折は、以下のとおり、可動域制限の最も一般的な原因の一つです。
- 関節内骨折による関節面の不適合:骨折線が関節面にかかる場合、骨片のわずかな転位(ズレ)や陥没が、関節面の滑らかさを損ない、関節の動きを物理的に阻害します。
治癒過程で関節面に段差や変形が残ると、変形性関節症を二次的に引き起こし、恒久的な可動域制限の原因となります。 - 長期固定による軟部組織の拘縮:骨折治療においてギプスや装具で患部を固定する期間が長期化すると、関節包や周囲の靭帯、筋肉などの軟部組織が線維化し、弾力性を失います(拘縮)。
これが、骨折が完全に癒合した後も関節の動きを制限する主要な要因となります。 - 異所性骨化:重度の外傷後、関節周囲の腱や筋肉などの軟部組織内に異常な骨組織が形成され、関節の動きを物理的にブロックすることがあります。
なお、以下の記事で、骨折の後遺症と後遺障害認定や、骨折の後遺症でもらえる慰謝料、適切な賠償金を得るポイントなどについて詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。
橈骨遠位端骨折による可動域制限の原因
手首に近い橈骨(とうこつ)の骨折で、転倒時に手をついた際に生じやすい外傷です。
交通事故による橈骨遠位端骨折で可動域が制限される原因として、以下のような傷病が挙げられます。
- 骨の変形・短縮:骨折後の不適切な整復や治癒による橈骨の変形(不正癒合)や短縮が、手関節の適合性を悪化させ、特に掌屈(手のひら側に曲げる)と背屈(手の甲側に反らす)、さらに前腕の回内・回外(ねじる動き)を制限します。
- 周囲軟部組織の拘縮:手関節周囲の関節包や靭帯の拘縮、あるいは合併した腱損傷後の瘢痕組織の形成が、制限の主要な原因となります。
なお、以下の記事で、橈骨遠位端骨折や発生原因と症状、橈骨遠位端骨折の後遺障害、慰謝料などについて詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。
上腕骨近位端骨折による可動域制限の原因
肩関節近くの上腕骨の骨折は、高齢者によく見られる傷病ですが、交通事故などの高エネルギー外傷でも生じます。
上腕骨近位端骨折による可動域制限の原因として、以下のものがあります。
- 骨片の転位と不正癒合:骨折片が大きくズレたまま癒合すると、骨頭の形が変わり、肩関節の動きの軌道を物理的に妨害します。
- 関節包・腱板の拘縮:骨折に伴う炎症や、治療のための長期間の肩の固定により、肩関節を包む関節包が硬化し、挙上、外転、外旋が大きく制限されます。
これは、肩関節の機能障害として後遺障害認定の対象となります。
なお、以下の記事で、上腕骨近位端骨折による後遺障害や、後遺障害の基準、賠償例などについて解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。
可動域制限の治療
可動域制限(ROM制限)の治療は、交通事故などで生じた機能障害を最小限に抑えるための極めて重要なプロセスであり、その核心はリハビリテーション(運動療法)にあります。
原因が器質的損傷(骨・靭帯の変形)や軟部組織の拘縮である場合、専門の理学療法士の指導のもと、複合的な治療が実施されます。
治療の中心は運動療法で、硬化した組織の柔軟性を回復させるストレッチング、特に他者の介助による他動的ストレッチングが不可欠です。
これに加えて、自力・介助による関節可動域訓練(ROM訓練)で可動範囲を広げ、筋力トレーニングで関節の安定性と実用的な可動域の向上を図ります。
運動療法の効果を高めるために、血流改善や筋肉の緊張緩和を目的とした物理療法(温熱療法など)や、疼痛をコントロールするための薬物療法・注射が併用されます。
そのうえで、保存的治療を尽くしても改善しない重度の器質的制限に対しては、外科的治療(関節形成術、関節授動術、人工関節置換術など)が最終的に選択されます。
可動域制限の後遺障害認定の要件
交通事故や労災事故によって生じた可動域制限が、法的な後遺障害として認定され、賠償の対象となるためには、単に関節の動きが悪いという事実だけでは不十分であり、厳格な要件を満たす必要があります。
可動域制限の程度は、原則として、他者の介助によって関節を動かした際の他動的関節可動域(PROM)の測定値に基づき、健側(障害のない側)の可動域と比較して評価されます。
この制限の程度によって、自賠責保険における後遺障害等級が以下のいずれかに分類されます。
- 「用を廃したもの」:関節が完全に動かないか、可動域が健側の10%以下に制限されている状態、または人工関節・人工骨頭挿入置換後の可動域が健側の2分の1以下に制限されている状態
- 「著しい機能障害」:関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されている状態、または人工関節・人工骨頭を挿入・置換した状態
- 「機能障害」:関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されている状態
特に、関節の可動域は分度器(角度計)を用いて測定されるため、わずかな測定誤差が等級認定の可否や等級の上下に直結します。
そのため、後遺障害診断書を作成する際には、必ず熟練した医師や理学療法士が正確に他動的関節可動域を測定し、その結果を詳細に記載してもらうことが、重要です。
可動域制限による慰謝料等の賠償金
可動域制限の慰謝料
可動域制限によって請求できる慰謝料には、以下のようなものがあります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝
まず、入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故による負傷で実際に入通院した期間に対して支払われる精神的苦痛を償うための費用です。
後遺障害の有無にかかわらず発生する項目ですが、適切な金額を請求するためには、医師の指示に基づき、不必要に長期化させることなく、継続的かつ適切な治療を行うことが重要となります。
弁護士に依頼することで、裁判の基準に近いとされる弁護士基準(裁判所基準)を適用して請求することが可能となり、自賠責保険や任意保険の基準よりも高額な慰謝料が認められる傾向にあります。
また、後遺障害慰謝料とは、可動域制限が治療を尽くしても改善せず、後遺障害等級が認定された場合に請求できる慰謝料です。
これは、将来にわたって残る機能障害による精神的・肉体的苦痛を償うものであり、等級の数字が小さいほど(症状が重いほど)高額になります。
可動域制限の程度に応じて認定される等級が確定した後、その等級に応じて定められた金額(弁護士基準)を請求します。
可動域制限は客観的な測定値で等級が判断されるため、適切な測定と等級認定が、この慰謝料額を決定する最大の要素となります。
可動域制限で請求できるその他の賠償金
前述の慰謝料の他にも、可動域制限が残ったことで生じる以下のような損害についても請求できます。
- 逸失利益
- 休業損害
- 積極損害
「逸失利益」とは、可動域制限という後遺障害が残ったことにより、労働能力が低下し、将来にわたって得られなくなるであろう収入の減少分を補填するものです。
後遺障害逸失利益は、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と、被害者の基礎収入、および労働能力を喪失した期間(原則として症状固定時から67歳まで)を基に算出されます。
可動域制限の等級が重いほど(例えば8級など)、労働能力喪失率が高くなるため、請求できる金額も高額になります。
次に、「休業損害」とは、 交通事故による負傷の治療のために、事故前の収入を得られなくなった期間(入院・通院中)の減収分を補償するものです。
給与所得者だけでなく、個人事業主や、家事労働に従事する主婦(主夫)も対象となります。
そして、「積極損害」とは、治療関係費や通院交通費・宿泊費、付添看護費用、家屋・自宅の改造費など、事故によって実際に支出せざるを得なくなった費用を指します。
交通事故で可動域制限となった場合のポイント
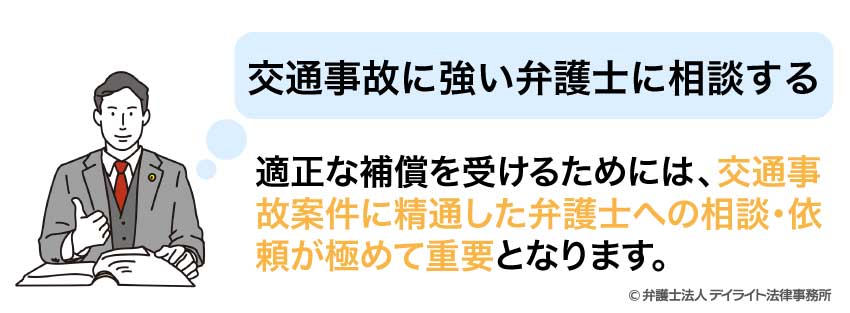
交通事故に強い弁護士に相談する
交通事故により可動域制限という重大な後遺障害を負った場合、適正な補償を受けるためには、交通事故案件に精通した弁護士への相談・依頼が極めて重要となります。
弁護士が交渉に加わることで、保険会社が提示する低額な「自賠責基準」や「任意保険基準」ではなく、裁判所が認める基準に最も近い「弁護士基準(裁判所基準)」を適用して慰謝料を請求することが可能となり、大幅な賠償金の増額が実現します。
また、可動域制限の等級認定は、画像所見(器質的原因)の立証と、正確な可動域の測定値が鍵となります。
弁護士は、後遺障害申請(被害者請求)において、認定に必須の書類に加え、可動域制限の原因を裏付ける有利な医学的資料を精査・添付するため、適正な等級認定を獲得できる可能性が高まります。
さらに、治療期間中や示談交渉における保険会社からの連絡や交渉を全て弁護士が代行するため、被害者は精神的なストレスから解放され、治療とリハビリに専念できます。
可動域制限についてのQ&A

関節可動域(ROM)の制限とは何ですか?
 関節可動域(ROM)の制限とは、外傷や疾病により、特定の関節を動かせる範囲が、正常な状態と比べて狭くなっている状態を指します。
関節可動域(ROM)の制限とは、外傷や疾病により、特定の関節を動かせる範囲が、正常な状態と比べて狭くなっている状態を指します。具体的には、関節が完全に曲げられない、または伸ばしきれないといった動作の制約が生じます。
この制限の程度は、他動的関節可動域(他者の介助で動かした場合の最大角度)を測定し、健側(障害のない側)と比較することで客観的に評価され、後遺障害認定の根拠となります。

なぜ乳がんで可動域が制限されるの?
 乳がんの手術、特に腋窩リンパ節郭清(えきかリンパせつかくせい)を行った後に、肩関節の可動域が制限されることがあります。
乳がんの手術、特に腋窩リンパ節郭清(えきかリンパせつかくせい)を行った後に、肩関節の可動域が制限されることがあります。これは、リンパ節の切除に伴い、周囲の大胸筋、小胸筋、神経などが損傷を受けることで、肩を動かす機能が低下するためです。
また、手術創の痛みやつっぱり感により、患者が無意識に腕を動かさない期間が長引く結果、関節包の拘縮が進行し、腕が挙がりづらくなる(肩関節可動域制限)ことも主要な原因の一つとされています。

人工膝関節置換術(TKA)後の可動域制限の原因は?
 人工膝関節置換術(TKA)後の可動域制限の主な原因は、手術による侵襲(組織の損傷)に伴う痛みや腫れ、そして術後の炎症です。
人工膝関節置換術(TKA)後の可動域制限の主な原因は、手術による侵襲(組織の損傷)に伴う痛みや腫れ、そして術後の炎症です。これらの反応によって関節周囲の筋肉に緊張が生じたり、筋力が低下したりすることが可動域を妨げます。
また、手術部位の組織が治癒する過程で生じる癒着や瘢痕化(傷跡が硬くなること)が物理的な制限因子となることがあります。
まとめ
可動域制限は、関節の動きが制限され日常生活に重大な支障をきたす後遺症であり、その原因の多くは骨折後の変形や軟部組織の拘縮といった器質的変化にあります。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、他動的関節可動域の正確な測定と、器質的原因を裏付ける医学的証拠の立証が不可欠です。
この認定結果に基づき、被害者は、後遺障害慰謝料や、労働能力の喪失に対する逸失利益など、多岐にわたる賠償金を請求する権利を有します。
適正な賠償金を得るためには、交通事故に精通した弁護士による専門的なサポートが不可欠です。
当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、被害者を強力にサポートしています。
弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。
LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害でお困りの方は、お気軽にご相談ください。