高次脳機能障害の診断テストとは?チェックリストを紹介
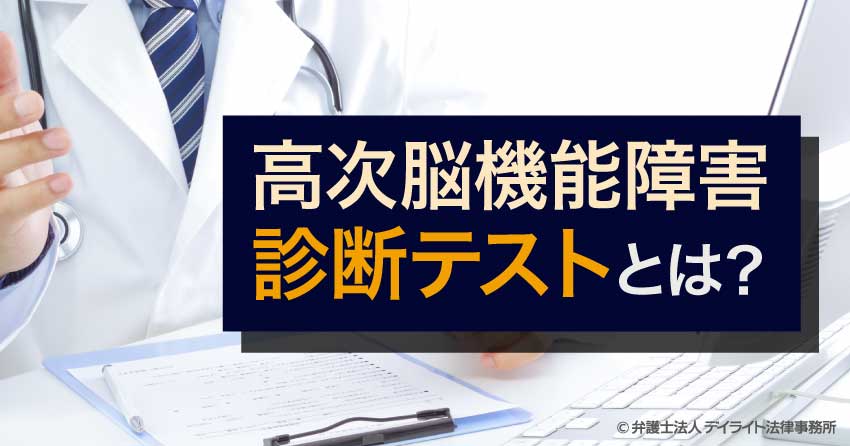
高次脳機能障害が疑われる場合には、病院で、脳の器質的病変の有無、知能、記憶、情報処理能力、遂行機能、言語などについて調べるため、各種の検査(画像検査、診断テスト等)を受けていきます。
さらに、交通事故での高次脳機能障害について後遺障害等級認定を受けようとする場合は、「日常生活状況報告書」という書式にある診断テストのチェックリストに回答していかなければなりません。
この「日常生活状況報告書」の診断テストは、医師や本人ではなく、家族や近親者、介護をしている人が回答するものとなっています。
ここで適切な回答ができていないと、後遺障害等級認定の際に不利になることもあります。
今回の記事では、高次脳機能障害の診断テストとは何か、回答する際の注意点、事故で高次脳機能障害を発症してしまった場合の対応方法を解説し、「日常生活状況報告書」の診断テストでのチェックリストの項目についてご紹介していきます。
目次
高次脳機能障害の診断テストとは?
高次脳機能障害とは、脳の高次脳機能に発生した障害のことをいいます。
高次脳機能障害は、医師などにとっても、外から見るだけでは見つけにくい障害だと言われています。
高次脳機能障害があると、次のような症状が生じます。
- 注意障害(気が散るなど)
- 記憶障害(覚えることができない、思い出せないなど)
- 遂行機能障害(段取りが悪くなる、計画的に行動できないなど)
- 社会的行動障害(感情をコントロールできなくなるなど)
このような症状の有無、内容、程度について調べるため、チェックリスト・診断テストが用いられています。
病院で行う検査(診断テスト)としては、次のようなものがあります。
- 知能検査
例:ミニメンタルステート検査(MMSE)、改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)ウェクスラー成人知能検査(WAIS-Ⅳ) - 記憶検査
例:ウェクスラー記憶検査(WMS-R)、リバーミード行動記憶検査(RBMT) - 言語機能検査
例:標準失語症検査(SLTA) - 注意力検査
例:TMT線引きテスト - 遂行機能検査
例:遂行機能の行動評価法(BADS)
これらの検査に加え、CT、MRIによる画像検査も行うことが多いです。
また、交通事故で高次脳機能障害を負った場合には、後遺障害等級認定を受けるため、「日常生活状況報告書」という書類に書かれたチェックリストに沿って、症状について回答していくという診断テストを行うことが必要になります。
この日常生活状況報告書は、医師や本人ではなく、ご家族や近親者又は介護をしている方が記入する必要があります。
高次脳機能障害のチェックリスト
日常生活状況報告書のチェックリスト
高次脳機能障害について評価するために作成する「日常生活状況報告書」のチェックリストは、次のようなものになっています。
回答する側は、①日常活動、②問題行動については、これらの項目について、各能力の程度、問題行動の頻度に対応する0~4の数字又はN(当てはまらない)を選び、回答していきます。
③ 日常の活動及び適応状況の項では、該当する項目を選び、○をつけていきます。
⑥ 身の回り動作能力については、自立の程度に応じて、1~4で評価していきます。
① 日常活動
- 1 起床・就寝時間を守れますか。
- 2 日課にしたがった行動をしていますか。
- 3 言葉による指示を理解できますか。
- 4 言いたい内容を相手に十分伝えられますか。
- 5 電話や来客の意図を理解して相手に応対し、家族へ適切な伝言ができますか。
- 6 適当な量の食事を適切な食事時間に食べていますか。
- 7 簡単な食事の準備から調理、配膳や食器洗いができますか。
- 8 部屋の掃除や整理、後片付けなどができますか。
- 9 洗剤の準備や洗濯機の操作、洗濯物干し、取り入れ、片付けなどができますか。
- 10 通勤や通学あるいは通院などのときに、安全に行き帰りできますか。
- 11 交通機関の利用で、切符購入、乗車、乗り換え、目的地での降車などができますか。
- 12 施設や病院等との連絡・調整、役所での必要書類の作成などができますか。
- 13 日用品程度の物品を選んで、買い物ができますか。
- 14 日常生活に必要な金銭管理ができますか。
- 15 体調を適切に判断して、体調不良の相談をしたり、簡単な傷の処置ができますか。
- 16 服薬の必要性を理解し、服薬の時間、量を間違わず、飲み忘れがないですか。
- 17 病院受診について、治療の必要性などの理解や判断ができていますか 。
- 18 保険証や預金通帳、財布などの大切な物の管理ができますか。
- 19 他人からの借り物やレンタルビデオなどの返却ができますか。
- 20 タバコの火やガスの始末、家の戸締りなど安全のための管理ができますか。
- 21 メモ帳やカレンダーを利用して予定を管理できますか。
- 22 キャッチセールス、ダイヤルQ2 迷惑メールなどに適切に対応できますか。
- 23 落し物、金銭の不足、道に迷うなどの日常生活で問題が起きた時に対処できますか。
- 24 円滑な対人関係を保っていますか。トラブルはないですか。
- 25 人と付き合う場合に、社会常識や基本的マナーに基づいた行動をしていますか。
(修学している場合に必要な項目。これらの項目については学校に確認することをお勧めします。) - 26 毎日の授業についていけますか。補習が必要になっていますか。
- 27 学校から家庭へ向けたお知らせを、忘れずに家族に告げられますか。
- 28 休み時間や放課後に、沢山の友達と話したり、遊んだりしていますか。
- 29 翌日の授業のための準備ができますか。
- 30 休まずに学校に行って、授業も普通に受けていますか。
② 問題行動
- 1 顕著な子どもっぽさ、年齢にそぐわない甘えや依存がありますか。
- 2 ムッとする、怒る、イライラなどの表情や態度がみられますか。
- 3 大声や奇声あるいは不適切な発言など、場にそぐわない言動がありますか。
- 4 他傷・自傷、あるいは物を壊すなどの暴力をふるうことがありますか。
- 5 菓子や食べ物、酒やタバコなどは誰かに注意されるまでやめることができないですか。
- 6 うまく行かないことがあると、家族や友達、あるいは同僚の責任にしますか。
- 7 手をいつまでも洗っている、電気を消して回るなど、強いこだわりがありますか。
- 8 他人が迷惑と感じるような強い思い込みがありますか。
- 9 じっとしていられずに、落ち着き無く動き回ったりしますか。
- 10 周囲に恐怖を与える行動や、盗みなどの行為がありますか。
③ 日常の活動及び適応状況(該当する項目に〇をつける)
- 1 家庭、地域社会、職場、または学校などの広い領域において、問題なく良く活動・適応している。
- 2 家庭、地域社会、職場、または学校で、効率良く順調に活動・適応している。
- 3 家庭、地域社会、職場、または学校における行動や人間関係に、ごくわずかな障害がある。
- 4 家庭、地域社会、職場、または学校で、いくらかの困難がある。しかし全般的には良好にふるまっていて有意義な対人関係もかなりある。
- 5 家庭、地域社会、職場、または学校で、中等度の困難がある。
(例:友達が少ししかいない。友人あるいは職場の同僚とトラブルを起こすことがある。) - 6 家庭、地域社会、職場、または学校で深刻な障害がある。
(例:友達がいない。仕事が続かない。) - 7 家庭、地域社会、職場、または学校で、重大な障害がある。
(例:友人を避け、家族を無視し、仕事ができない。子供の場合、しばしば乱暴をし、家庭では家族に反抗し、学業は同級生についてゆけない。) - 8 家庭、地域社会、職場、または学校で、役割を果たしたり、人と関わることができない。
(例:家屋内あるいは自室に引きこもり。仕事も家庭も友人関係も維持できない。) - 9 最低限の身辺の清潔や健康維持もできない部分がある。一人ではほとんど生活を維持できない。
- 10 最低限の身辺の清潔や健康維持を持続的に行うことができない。
④ 社会生活・日常生活への具体的な影響
①~③の症状状態が、社会生活・日常生活にどのような影響を与えているか、事故前後の生活状況の変化、現在支障が生じていることなどを、具体的に記入する(自由記載。別紙を添付してもよい。)
⑤ 就労・就学状況
就労状態・就学状況を記載する。
記載するに当たっては、事故前と現在の状況を、それぞれ記載する。
仕事や学校を辞めた場合、あるいは変えた場合には、その理由やいきさつを記入する。
⑥ 身の回り動作能力
- 食事動作
- 更衣動作
- 排尿・排尿動作
- 排便・排便動作
- 入浴動作
- 屋内歩行
- 屋外歩行
- 階段昇降
- 車いす操作
- 公共交通機関
(*自立の程度に応じて、1~4で評価する。)
⑦ 見守り等が必要な理由など
⑥に基づき、声かけ、見守り、介助が必要な理由、それらの内容、頻度を具体的に記入する(自由記載)。
高次脳機能障害の診断テストの注意点
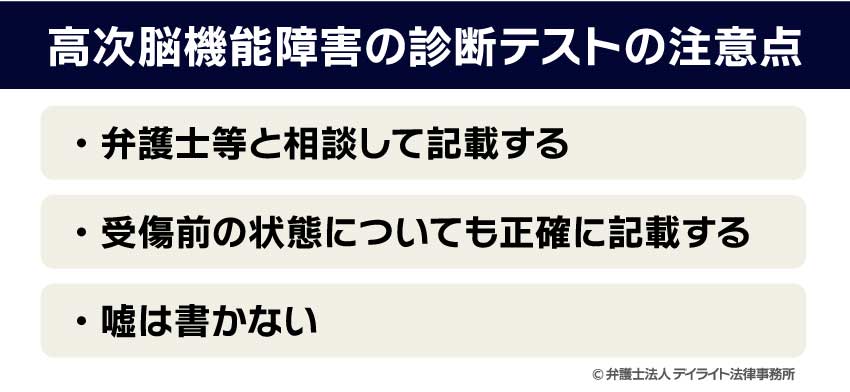
弁護士等と相談して記載する
高次脳機能障害を交通事故の後遺障害と認めてもらうことは、簡単ではありません。
後遺障害と認定される可能性を上げるためには、日常生活状況報告書の診断テストに正確に答えることがとても重要になります。
正確な回答をしていくためには、高次脳機能障害での後遺障害等級認定にくわしい医師や弁護士に相談することをお勧めします。
正確な回答とならない例としては、①日常活動、②問題行動については0~4又はN(当てはまらない)で回答する必要があるところを、「実際に表れている症状が、0~4又はNのどれに該当するのか」を十分に理解しておらず、正確に回答することができないというものがあります。
本来であれば「3」とすべきところを、誤解により、より軽い「2」と記入してしまうようなことです。
このような回答をしてしまうと、後遺障害等級認定の際に不利になってしまいかねません。
こうした事態を避けるためにも、日常生活状況報告書を書く際には、高次脳機能障害の後遺障害等級認定にくわしい弁護士等と相談することをお勧めします。
受傷前の状態についても正確に記載する
高次脳機能障害の診断テストの際には、受傷後(現在)の状況だけでなく、受傷前の状況についても記載しなければならない部分があります。
これは、受傷前からあった症状(障害)か、受傷によって生じた障害かを明らかにする必要があるためです。
このように、受傷前の症状に関する答えも、後遺障害等級認定の際に重要になりますので、高次脳機能障害の後遺障害等級認定にくわしい弁護士等に相談しながら、正確に答えるようにしましょう。
嘘は書かない
いくら「日常生活状況報告書にどう記入するかが後遺障害等級認定に重要である」といっても、嘘をついて症状をより悪く見せようとするようなことは止めましょう。
日常生活状況報告書の記載とカルテなどの記載や検査結果が整合しないと、「この被害者は嘘をついている」「この日常生活状況報告書に書かれていることは信用できない」などと思われ、適切な認定を受けることが難しくなるおそれがあります。
日常生活状況報告書には、正確な内容を記載しましょう。
事故で高次脳機能障害となった方の対応
事故で高次脳機能障害となってしまった場合には、次のような対応を取ることが考えられます。
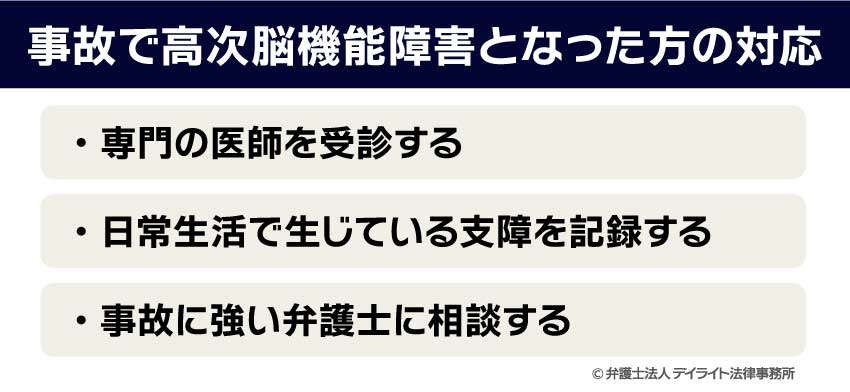
専門の医師を受診する
事故で頭に衝撃を受けた、事故後意識がなくなったなどといったことがあった場合には、事故後に高次脳機能障害を発症するおそれがあります。
ところが、高次脳機能障害は、「見えない障害」とも呼ばれており、見落とされがちな障害となっています。
高次脳機能障害にくわしくない限り、医療関係者にとっても、
- 外見からは症状が分かりづらい
- 画像診断では見つけられない場合もある
などといったことにより、診断のつけにくいことが珍しくない障害なのです。
高次脳機能障害の可能性がある場合は、必要な検査を十分に受けて適切な診断を出してもらい、症状についても十分にカルテに残してもらうためにも、早めに高次脳機能障害にくわしい専門の医師に診てもらえると良いでしょう。
日常生活で生じている支障を記録する
高次脳機能障害は、画像検査でも診断がつかない場合がある、見つけにくい障害です。
そのため、障害があることを医師などに分かってもらうためには、日常生活にどのような支障が生じているのかを詳しく説明できることが大切です。
医師に十分説明できるようにするためにも、日常生活で生じている支障については、日記やメモなどに残すようにしましょう。
症状があらわれている状況を動画などで撮影するのもよいかもしれません。
こうした日常生活に関する記録は、後遺障害等級認定を受ける場合にも重要になってきますので、できるだけ記録を残していくことをお勧めします。
事故に強い弁護士に相談する
事故で高次脳機能障害になったと考えられる場合は、適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、証拠となる資料を揃え、ポイントを押さえた主張を整えなければなりません。
こうした準備を十分に行うためには、事故に強い弁護士に相談・依頼することが大切になります。
弁護士に依頼することには、上に挙げたほかにも次のようなメリットがあります。
- 被害者にとってもっとも有利な弁護士基準で賠償額を算定できるので、賠償金を増額できる(交通事故の場合)
- 適切な過失割合になるように交渉してくれる
- 医師への症状の伝え方、後遺障害等級認定のための書類を書いてもらう際のポイントなどについてアドバイスしてくれる
- 保険会社とのやり取りを任せることができる(交通事故の場合)
- 治療の打ち切りを伝えられた場合に、保険会社と交渉してくれる(交通事故の場合)
- 疑問や不安が出てきたときに、すぐに相談できる
事故を弁護士に依頼することのメリット、弁護士の選び方については、以下のページをご参照ください。
高次脳機能障害の診断テストについてのQ&A

高次脳機能障害の判断方法は?
 高次脳機能障害であるかどうかは、各種検査(画像検査、超音波検査、神経心理検査など)の結果、高次脳機能障害の症状(記銘障害、記憶障害など)の状況などをもとに判断されます。
高次脳機能障害であるかどうかは、各種検査(画像検査、超音波検査、神経心理検査など)の結果、高次脳機能障害の症状(記銘障害、記憶障害など)の状況などをもとに判断されます。さらに、交通事故によって高次脳機能障害が生じたというためには、事故後の意識障害の有無や意識障害が続いた時間、事故による頭部外傷の有無、事故前の生活状況と事故後の生活状況の違いについても主張立証する必要があります。
事故前の生活状況と事故後の生活状況については、記事でご紹介した「日常生活状況報告書」の診断テスト・チェックリストに回答することが必要になります。
なお、交通事故での高次脳機能障害について後遺障害等級認定を申請する際には、画像検査の結果の有無も重要な要素になります。

高次脳機能障害を調べるには?
 高次脳機能障害の有無、状態を調べるためには、病院で、神経心理検査として、認知機能を総合的に調べる検査(例:ミニメンタルステート検査(MMSE)、改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R))、脳の領域ごとに機能を調べる検査を行います。
高次脳機能障害の有無、状態を調べるためには、病院で、神経心理検査として、認知機能を総合的に調べる検査(例:ミニメンタルステート検査(MMSE)、改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R))、脳の領域ごとに機能を調べる検査を行います。さらに、より詳細な検査として、頭部MRI検査やCT検査と言った画像検査も行います。
画像検査で異常が見つからない場合でも、脳の血流を調べる脳血流シンチグラフィ、脳波検査などを行って、異常を発見できることもあります。
参考:高次脳機能障害 (こうじのうきのうしょうがい)とは | 済生会
まとめ
今回は、高次脳機能障害の診断テスト、回答する際の注意点などについて解説しました。
事故で高次脳機能障害になってしまった場合、後遺障害等級認定を受けて適切な賠償を得るためには、事故にくわしい弁護士に相談・依頼し、専門的な観点から、効果的な主張・立証をしてもらうことが重要です。
当事務所では、事故による人身障害を集中的に取り扱う人身障害部を設け、高次脳機能障害による後遺障害等級認定のサポートに尽力しています。
電話・オンラインによる全国からのご相談もお受けしております。
お困りの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。



