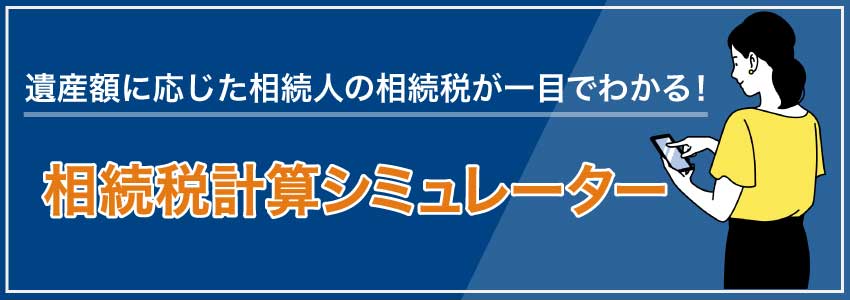
相続税の計算はとても複雑で、一般の方が自分で計算するのは大変です。
下記は、デイライト法律事務所が開発した相続税の概算をシミュレーションできる計算機です。
ご入力いただくことで相続税の概算が算出可能ですので、下記の注意事項をご確認の上、ご活用ください。
被相続人(亡くなった方)に関して、以下の項目にご入力ください。
| 相続人 | 相続割合 | 相続する遺産の額 | 相続税の額 |
配偶者 |
※複数名の場合は1名の金額を表示しております
注意事項
※遺産総額とは
より正確に算出したい場合は、基礎控除前の課税価格を入力してください。課税価格とは、遺産から借金や葬式費用などを控除した額です。
課税価格についての詳しい解説はこちら
※法定相続割合とは
法定相続割合とは、法律で定められた相続分の割合であり、下表はこれをまとめたものです。法定相続割合は一応の目安ですので、これと異なる合意(遺産分割協議)を行うことも可能です。法定相続割合と異なる割合で合意する場合は「手入力」を選択してください。
| 相続人 | 法定相続割合 |
| 配偶者と子 | 配偶者2分の1 子2分の1 |
| 配偶者と直系尊属(両親など) | 配偶者3分の2 直系尊属3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
| 配偶者のみ、又は、子のみ | 配偶者、又は、子がすべて |
| 直系尊属のみ又は兄弟姉妹のみ | 直系尊属のみ又は兄弟姉妹がすべて |
法定相続割合について詳しい解説はこちら
※代襲相続人とは
子供や兄弟姉妹が死亡している場合、その子供が相続人となり、これを代襲相続人といいます。代襲相続人が死亡している場合に、さらにその子供が遺産を相続することを再代襲相続といいます。なお、兄弟が相続人となる場合、再代襲相続はありません。
※相続放棄がある場合
相続放棄をする方がいる場合、その方は人数に含めずに算定してください。
なお、相続放棄の場合、代襲相続はしません。
(免責事項)
この自動計算機は、簡易迅速に相続税を算定することを目的としているため、正確ではありません。
また、この自動計算には下記のような問題点があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、正確な相続税の額については相続問題に精通した弁護士にご相談されるようにしてください。
相続においては、遺産の範囲を調査し、かつ、適切に評価しなければなりません。特に遺産に不動産や非上場会社の株式がある場合、評価が難しく専門家の評価がポイントとなります。
例えば、被相続人が孫を養子とした場合、相続税が2割増しになるなどの例外があります。また、未成年者や障害者がいる場合は税金から控除されますがこれらの事情は考慮しておりません。
- 再代襲相続には対応していない
- 相続税の総額を計算する際に1000円未満を切り捨て(相続税基本通達16−3)
- 按分割合の端数処理(相続税基本通達17−1)は行わずに計算
- 相続割合については小数第3位を四捨五入
- 税額控除は配偶者控除のみ実施
当事務所には、相続問題に注力する弁護士と税理士のみで構成される相続対策チームがあり、相続問題に直面されている方々を強力にサポートしています。
遠方の方については、LINEなどを利用したオンライン相談も可能です。相続問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
無料相談の流れはこちらから
