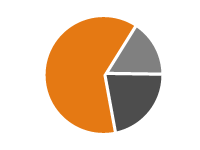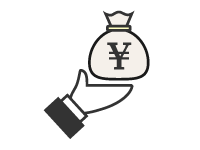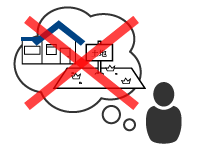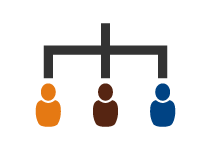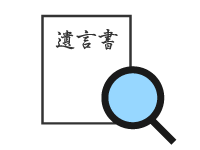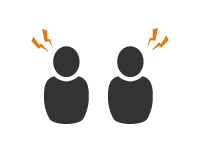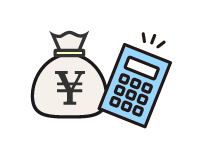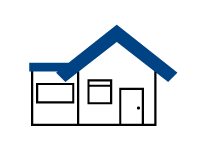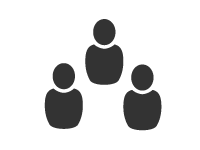- 思っていたより預貯金が少ない
- 相続人による預貯金の使い込みが発覚した
- 預貯金の使い込みをしたと疑われて困っている
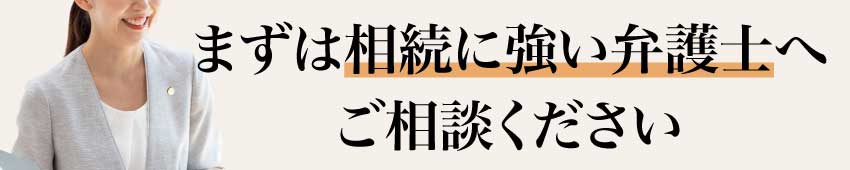
目次
預貯金の使い込みとは
預貯金の使い込みとは、被相続人(亡くなった方のこと)の預貯金を本人に無断で使うことをいいます。
このような預貯金の使い込みは、①生前の使い込みと、②死後の使い込みの2つの種類があり、それぞれで状況が異なります。
当事務所に寄せられるご相談の典型例としては、次のようなものです。
 相談者A
相談者A母と一緒に生活していた姉が不正に出金して着服した可能性がある。
 相談者B
相談者B父と一緒に生活していた母に問いただすと、知らぬ存ぜぬという態度で話にならない。
 相談者C
相談者C父の死後、財産がほとんどないことについて、兄は「父のために使った。」と話しているが、信じられない。
親の通帳からの使い込みは罪となる?
被相続人(亡くなった方)の預貯金の使い込みは、基本的には、横領罪、又は、窃盗罪などの犯罪に該当する可能性があります。
しかし、子供が親の通帳から預貯金を引き出して使い込んだ場合、法律上、その刑が免除されます(刑法244条・251条)。
根拠条文:刑法|電子政府の窓口
したがって、刑事責任ではなく、民事責任を追求していかなければなりません。
預貯金の使い込みを取り戻す際の難点
①使い込んだ額がわからない
預貯金を使い込んだ相手に返還を求める前提として、「預貯金の減った額」がわからないといけません。
手元に、被相続人(亡くなった方)の通帳があれば、記載内容を見ると、ある程度の推測はできるかもしれませんが、正確には難しい場合が多いでしょう。
手元に通帳がない場合、素人の方が調査するのは非常に困難です。
②相手が使い込みを認めていない
「預貯金の減った額」がある程度わかったとしても、それだけでは返還請求は認められません。
例えば、
裁判において、「父が亡くなる直前、預貯金から100万円が引き出された」ことを立証できても、それだけでは裁判所は勝たせてくれません。
なぜならば、預貯金は、本人(父)が管理しているのが通常なので、100万円は本人が引き出したと考えるからです。
したがって、「預貯金の減った額」に加えて、「相手が使い込んだ」ことを主張し、立証しなければなりません。
しかし、使い込みについて、相手が素直に認めないことは多く、その場合、返還請求が認められないこともあります。
例えば、
父が要介護状態で一人であることはできなかった、相手が父と一緒に生活して財産を管理していた、などの事実が立証できれば「相手が使い込んだ」と認定される可能性があります。
しかし、その立証は決して簡単ではありません。
預貯金の使い込みについてよくあるQ&A
当事務所の相続対策チームに相談するメリット


相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。


日本では、一つの分野に注力する専門性ある弁護士はまだ少ないのが現状です。
当事務所は、相続の相談は、専門の相続対策チームに所属する相続弁護士が対応いたします。
相続対策チームは、預貯金の使い込み問題についても多くの相談を受けており、高度な専門知識に加えて、豊富な経験に基づくノウハウを有しています。


しかし、裁判は、判決がでるまでに長期間と多大な労力を必要とします。
しかも、預貯金の使い込みの事案は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所が管轄となるため、遺産分割調停と並行する場合、弁護費用も割高となることが多くあります。
当事務所の相続弁護士は、紛争を早期に解決するために、まずは、代理交渉を行います。
これは、弁護士が依頼者の代理人となって、相手方と交渉する方法です。
当事者同士では解決できなくても、弁護士が間に入ることによって、預貯金の返還に応じてくれる可能性もあります。
これにより、紛争を早く解決できる可能性があります。


当事務所の相続弁護士は、遺産分割等の手続も合わせてサポートしています。


当事務所の相続対策チームには、税理士資格を有する弁護士が所属しています。
返還を求められている方へのサポート
遺産をきちんと管理していたのに、親族が感情的になってしまい、不正に出金したと疑われるケースもあります。
また、確かに、出金はしたけど、これまで被相続人(亡くなった方)の世話をしてきたことから、正当な権利があると判断して出金したというケースも考えられます。
このようなケースでは、相手を無視してしまうと、刑事告訴、民事訴訟などを提起され、事態が悪化してしまうおそれがあります。
当事務所では、このような返還を求められている方に対しても、今後の対策について、親身にご相談に乗らせていただいています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士費用
相談にかかる費用
(オフィスで対面での相談の場合)
預金の使い込み
| 項目 | 着手金(税込) | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 代理交渉 | 22~33万円 | 経済的利益の11% |
| 訴訟 | 追加分:22~33万円 | 経済的利益の16.5% |
※財産調査の必要性が高いなど、複雑な場合には、着手金の額を加算することがあります。
ご相談の方法
ご予約受付時間
365日年中無休・24時間対応しています。
法律相談のお時間
平日午前10時00分~午後9時00分
お悩み別サポート
遺産相続についてこのようなことでお困りではありませんか?