
遺留分侵害額の計算式を簡単に示すと、次のとおりとなります。
遺留分侵害額の計算式
遺留分侵害額 = 遺留分額 -(遺贈又は特別受益の価額)-(遺留分権利者が相続によって得た財産額:寄与分による修正は考慮しない)+(引き継ぐ借金の額)
遺留分侵害額の計算方法
遺留分権利者は、受遺者又は相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭支払いの請求ができます。
遺留分侵害額の計算式を簡単に示すと、次のとおりとなります。
遺留分侵害額の計算式
遺留分侵害額 = 遺留分額 -(遺贈又は特別受益の価額)-(遺留分権利者が相続によって得た財産額:寄与分による修正は考慮しない)+(引き継ぐ借金の額)
遺留分侵害額の算定方法について、民法は、上述した「遺留分額」から「遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与(特別受益)の価額」及び「第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額」を控除し、これに「被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(遺留分権利者承継債務)の額」を加算して算出することを定めています(1046条2項)。
遺留分侵害額の請求方法や手順については以下のページをご覧ください。
遺留分侵害額の計算のポイント
遺留分算定の基礎となる財産額の算定において、相続人対する特別受益は、相続開始前の10年間になされたものに限定されています。
しかし、遺留分侵害額を求める計算式においては、「特別受益の価額」を相続開始前の 10年間にされたものに限定せずに加算します。
これまでいくつも算定式が出てきました。
まとめると次のとおりとなります。
遺留分侵害額 = ★遺留分額 -(遺贈又は特別受益の価額)-(遺留分権利者が相続によって得た財産額:寄与分による修正は考慮しない)+(引き継ぐ借金の額)
★遺留分額 =(A:遺留分算定の基礎となる財産額)×(B:個別的遺留分の割合)
A:遺留分算定の基礎となる財産額 =(被相続人が相続開始の時において有した財産の価額)+(贈与財産の価額)-(相続債務の全額)
B:個別的遺留分の割合 = 総体的遺留分の割合 × 法定相続分の割合
ケース別に遺留分侵害額の計算方法を解説
遺留分侵害額の計算は、上記のとおり、やや複雑なため、なれていないと難しいです。
具体例をもとに、検討してみましょう。
具体例の中の個別的遺留分の割合の算定については下記の早見表を参考にされてください。
 【遺留分の早見表】
【遺留分の早見表】
| 相続人 | 個別的遺留分(各々の遺留分) | |||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子供※ | 親※ | 兄弟姉妹 | |
| ①配偶者のみ | 2分の1 | - | - | - |
| ②子供のみ | - | 2分の1 | - | - |
| ③親(いない場合は祖父母)のみ | - | - | 3分の1 | - |
| ④配偶者と子供 | 4分の1 | 4分の1 | - | - |
| ⑤配偶者と親 | 3分の1 | - | 6分の1 | - |
| ⑥配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | - | - | なし |
具体例 ケース①
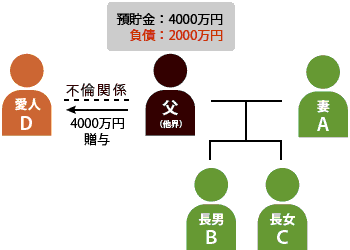 先日、夫が死亡し、相続人は妻である私(A)のほか、長男B、長女Cの3人がいます。
先日、夫が死亡し、相続人は妻である私(A)のほか、長男B、長女Cの3人がいます。
夫の遺産は、預貯金の 4000万円だけで、負債が 2000万円ありました。
夫は、亡くなる半年前に、愛人であるDに対し、4000万円を贈与していました。
私と子供たちは、どの程度、遺留分侵害額を請求できますか?
STEP1 遺留分算定の基礎となる財産額の算定
(相続開始時の財産)+(贈与財産の価額)-(相続債務の全額)
相続開始時の財産(4000万円)+ 贈与財産の価額(4000万円)- 相続債務(2000万円)= 6000万円
![]()
STEP2 個別的遺留分の割合の算定
上記の遺留分の早見表を参照
- 妻A 2分の1(総体的遺留分の割合)× 2分の1(法定相続分)= 4分の1
- 長男B 2分の1(総体的遺留分の割合)× 4分の1(法定相続分)= 8分の1
- 長女C 2分の1(総体的遺留分の割合)× 4分の1(法定相続分)= 8分の1
![]()
STEP3 遺留分額の算定
- 妻A 6000万円 × 4分の1 = 1500万円
- 長男B 6000万円 × 8分の1 = 750万円
- 長女C 6000万円 × 8分の1 = 750万円
![]()
STEP4 遺留分侵害額の算定
- 遺留分権利者が相続によって得た額
- 妻A 4000万円 × 2分の1(法定相続分)= 2000万円
- 長男B 4000万円 × 4分の1(法定相続分)= 1000万円
- 長女C 4000万円 × 4分の1(法定相続分)= 1000万円
- 引き継ぐ借金の額
- 妻A 2000万円 × 2分の1(法定相続分)= 1000万円
- 長男B 2000万円 × 4分の1(法定相続分)= 500万円
- 長女C 2000万円 × 4分の1(法定相続分)= 500万円
- 各々の遺留分侵害額
- 妻A 1500万円 - 2000万円 + 1000万円 = 500万円
- 長男B 750万円 - 1000万円 + 500万円 = 250万円
- 長女C 750万円 - 1000万円 + 500万円 = 250万円
回答 以上から、妻Aは 500万円、長男Bと長女Cは 250万円を愛人Dに請求できます。
具体例 ケース②
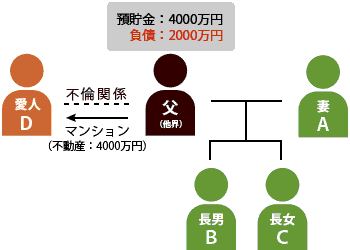 先日、夫が死亡し、相続人は妻である私(A)のほか、長男B、長女Cの3人がいます。
先日、夫が死亡し、相続人は妻である私(A)のほか、長男B、長女Cの3人がいます。
夫の遺産は、預貯金の 4000万円だけで、負債が 2000万円ありました。
夫は、亡くなる半年前に、愛人であるDに対し、4000万円の不動産(マンション)を贈与していました。
私と子供たちは、どの程度、遺留分侵害額を請求できますか?
ケース②は、ケース①と異なり、愛人Dへの贈与が金銭ではなく、不動産となっています。
このような場合、遺留分権利者は、愛人Dに対して、「何を」請求するかが問題となります。
従来、このようなケースでは、遺留分権利者の減殺請求によって、遺贈又は贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、受遺者又は受贈者が取得した権利は、その限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するとされていました。
上記の例では、不動産の価額は 4000万円であるところ、相続人らの遺留分侵害額は、妻Aは 500万円、長男Bと長女Cは 250万円なので、妻Aは 8分の1(500万円 ÷ 4000万円)、長男Bと長女Cは 16分の1(250万円 ÷ 4000万円)について、不動産の持ち分の減殺を求めることができます。
しかし、このような不動産の共有状態は、共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせることになると批判されていました。
そこで、相続法が改正され、不動産の共有持分を取得するのではなく、遺留分侵害額の請求権の行使によって、金銭債権が発生することになりました(改正法は2019年7月1日施行)。
したがって、上記の場合、ケース①と同様に、妻Aは 500万円、長男Bと長女Cは 250万円を愛人Dに請求できます。
ただし、金銭請求を受けたDが直ちに金銭を準備することができない場合も想定されます。
そこで、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求によって、同人らが負担する金銭債務の全部又は一部の支払について、相当の期限を許与することができるという制度が設けられました(民法1047条5項)。

