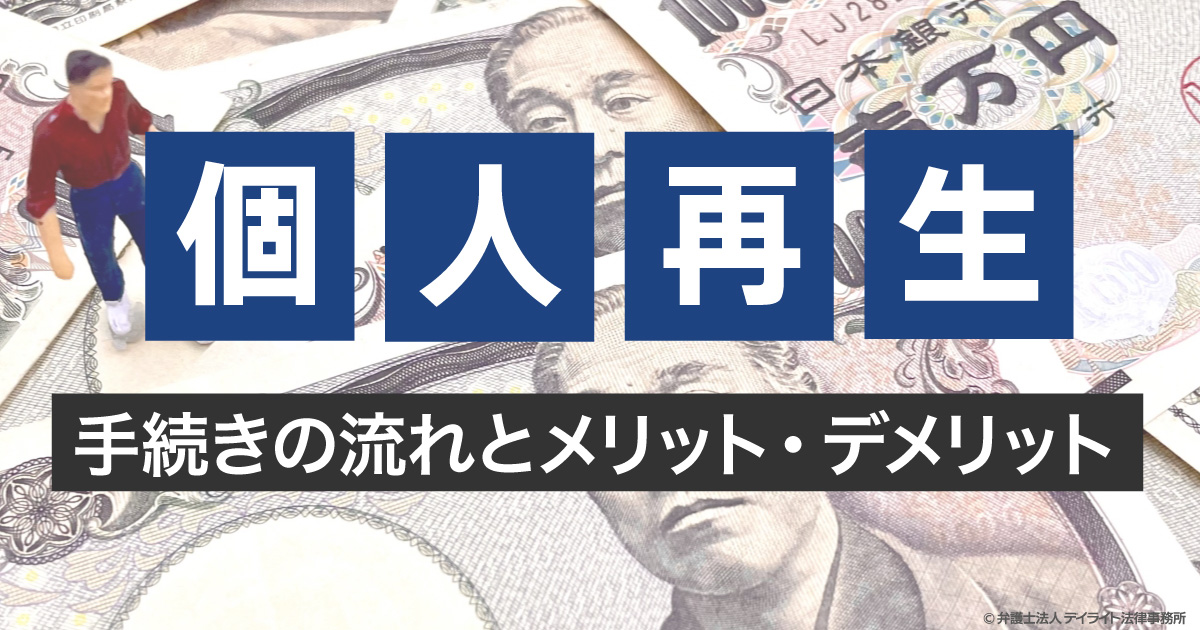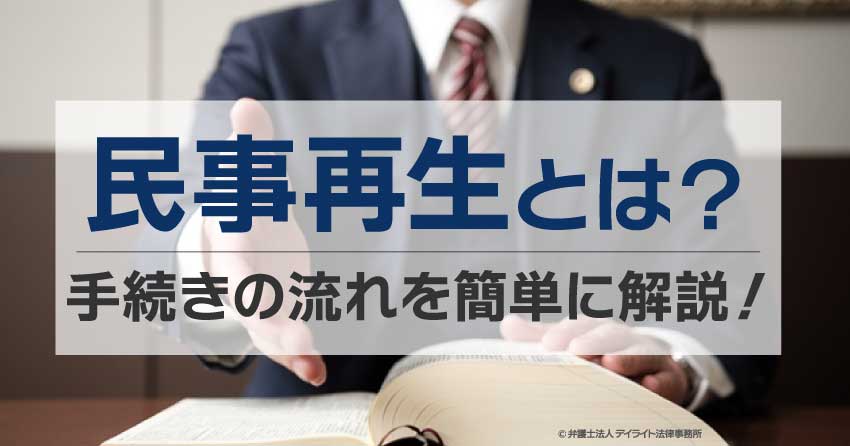
民事再生とは、民事再生法という法律に基づき、債権者の多数の同意のもと、裁判所の認可を受けて会社の再建を図る手続のことをいいます。
会社が倒産の危機に直面したとき、破産を選択する前に、まずは経営の立て直しを図ろうとすることは当然です。
したがって、民事再生は多くの会社で検討すべき法的手続きの一つとなります。
しかし、民事再生法は非常に複雑で一般の方が理解するのは簡単ではありません。
ここでは、企業の経営問題に注力する弁護士が民事再生のメリットや手続の流れについて、わかりやすく解説しています。
ぜひ参考になさってください。
民事再生とは
民事再生とは、民事再生法という法律に基づき、債権者の多数の同意を得て、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等によって、債務者の事業又は経済生活の再生を図る手続を言います(民事再生法1条)。
民事再生法とは
民事再生法は、経済的に苦しい債務者について、裁判所の監督のもと、債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする法律です(1条)。
再建を図るという点では、会社更生法と同じですが、会社更生法は株式会社のみを対象としているのに対し、民事再生法は個人から大企業まで幅広く対象としています。
民事再生と個人再生との違いとは?
民事再生と個人再生はよく混同されがちです。
両者の異同を示すと下表のとおりとなります。
| 要素 | 民事再生 | 個人再生 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 民事再生法 | 民事再生法 |
| 対象 | 個人のほかに会社などの法人も対象 | 個人のみ |
| 負債の上限 | なし | 5000万円以下(住宅ローンを除く) |
| 手続 | 複雑 | 簡略 |
| 裁判所に納める費用 | 高額:最低200万円〜 | 低額:最低数万円〜 |
民事再生と個人再生は、ともに民事再生法の手続であり、債務者の再建を図るという目的は共通しています。
両者の違いは、民事再生は会社などの法人でも個人でも利用できるのに対し、個人再生は個人しか利用できません(221条1項・239条1項)。
また、個人再生は、住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下の場合が対象となります(同)。
このような違いから、一般的に、会社の再生を図ることを民事再生と呼び、個人の再生を図ることを個人再生と呼んでいます。
個人の方でも、負債額が5000万円を超えると個人再生は利用できませんが、そのような例は稀です。
「民事再生」手続きは、法人や高額な負債を抱える個人を対象としているため、手続きは複雑です。
これに対し、「個人再生」は個人の方でも利用できる手続きであり、手続きが大幅に簡略化されています。
また、手続きの難易度の違いから、裁判所に納める金額も大きく異なります。
民事再生と会社更生との違いとは?
裁判所が関与する再建のための手続としては、民事再生の他に会社更生もあります。
両者の異同を示すと下表のとおりとなります。
| 要素 | 民事再生 | 会社更生 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 民事再生法 | 会社更生法 |
| 対象 | 個人のほかに法人も対象 | 株式会社のみ |
| 現経営陣 | 残ることが可能 | 退任する |
| 株主の権利 | そのまま | なくなる |
| 活用されるケース | 問わない | 大企業など |
| 裁判所に納める費用 | 高額:最低200万円〜 | 莫大:数千万円 |
民事再生は原則として、会社の経営陣が交代せずに会社の再建を図ります。
また、会社更生は株式会社のみが対象となりますが、民事再生はそのような限定はありません(会社更生法1条)。
そのため、民事再生は会社更生よりも現経営状態に与える影響は小さく、かつ、様々な事業主が利用できるといえます。
また、会社更生は比較的大企業などでより大掛かりな手続きとなるイメージです。
したがって、多くの企業では、会社更生よりも民事再生の方を検討することが多くなるでしょう。
もっとも、後述するように、民事再生には注意点があり、破産と比べて成功率は決して高いとはいえません。
民事再生のメリットとデメリット

民事再生のメリットとデメリットをまとめると、下表のようになります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
民事再生のメリットとは?
民事再生は、破産と異なり、会社の再建を目指す手続きです。
これまで築き上げた会社を残すことができるという点で、大きなメリットがあります。
債権者の多数の同意を得て、かつ、再生計画を裁判所がOKしてくれれば、債務を大幅に圧縮させることが可能です。
民事再生は原則として経営陣の交代はありません。
民事再生のデメリットとは?
民事再生は法的整理の一つです。
民事再生を行うということを取引先が知れば、信用を失い、契約打ち切りなどになる可能性があります。
民事再生は裁判所や弁護士に対して、数百万円の費用が必要となることが見込まれます。
抵当権などの担保権については、民事再生の手続によっても当然に止めることはできません。
民事再生の手続きの流れ

民事再生は、債務者等が裁判所に申立てを行い、裁判所が再生手続開始決定を下すことで始まります。
その後、債務者の資産調査や債権届・債権調査などが行われます。
そして、再生計画案が作成されます。
その再生計画案が債権者によって可決され、裁判所の認可を受けることで再生計画案が正式に成立します。
民事再生の申立てから開始決定までの間に、情報を嗅ぎつけた債権者が強硬に債権回収を行う可能性があるため、実務上、弁済禁止の保全処分を発令する。

通常、倒産手続に精通した弁護士を監督委員に選任。
債務者は財産の処分、借り入れなどについて監督委員の同意を得なればならない。

「再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき」など、一定の場合申立てが棄却される。
申立てから開始決定まで通常は2週間程度。

債権者が再生手続に参加するためには、裁判所が定める期間内に債権届出を行うことが必要

申立人(再生会社)は、裁判所に対し、財産価額の評定や財産状況の報告を行う。

申立人(再生会社)は、債権届出があった債権の認否を行い、その結果を裁判所の提出する。

申立人(再生会社)は、裁判所に対し、再生計画案を作成して提出する。
債権者に対する「弁済率」は、最低限、仮に再生会社が倒産した場合の配当を上回るものでなければならない。

再生計画案について債権者集会で決議を行う。
可決には次の2つを満たす必要がある。
- 議決権者の過半数の同意(頭数要件)
- 議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意(議決権数要件)
申立てから認可まで通常は5か月程度

再生計画が可決すると、弁済がスタート。
監督委員は3年間、再生計画の遂行を監督する。
民事再生の注意点
社長が退任する場合もある?
民事再生は、会社の事業の再生を図る手続ですので、通常の場合、経営陣の変更はありません。
しかし、民事再生は、債権者の多数の同意がなければ手続を進めることができません。
そのため、債権者の納得を得るために、社長の退任などが必要となる場合があります。
民事再生のハードルは高い?
民事再生は、次のいずれかに該当する場合、開始決定が出されることなく棄却されてしまいます(民事再生法25条)。
- 再生手続の費用の予納がないとき。
- 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
- 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
- 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
また、開始決定がなされても、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合裁判所は職権で破産手続きに移行させることができます(民事再生法250条)。
このようなことから、民事再生のハードルは決して低くはないといえるでしょう。
一律に弁済が禁止される
民事再生は、一定額以下の少額債権を除き、債権者への弁済が禁止されていまします。
この債権者には、金融期間だけでなく、商取引による債権者も含まれます。
したがって、取引先には「倒産した」とのマイナスイメージが生じるでしょう。
取引先の信用を失い、取引の終了などによって企業価値の著しい毀損も予想されます。
民事再生が成功する3つのポイント
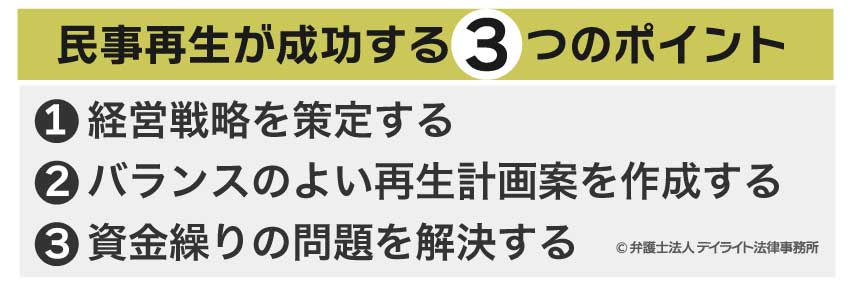
POINT1経営戦略を策定する
民事再生は、会社を「再建」するために行うものです。
そのためには、負債の問題をクリアすれば、企業が成長し、発展する見込みがなければなりません。
わかりやすく言えば、「儲け」を出すことができるか否かが重要です。「儲け」を出せなければ、ただの延命措置にすぎず、周囲に迷惑をかけるだけになるでしょう。
「儲け」を出す方法は2つです。
一つは売上を増加させることです。
もう一つは、コストを削減することです。
売上の増加やコスト削減のためには、まずは自社の置かれた環境を冷静に分析しなければなりません。
環境分析においては、上述した企業価値の毀損も考慮すべきです。
そして、企業価値の毀損を克服し、効果的かつ具体的なアクションプランを策定することがポイントとなります。
POINT2バランスのよい再生計画案を作成する
再生計画案は、倒産しかけた会社について、どのようにして再生させるかを策定したプランです。
この再生計画案が裁判所や債権者に認められるかによって、民事再生の成否が決まります。
そのために、債権者の同意を得られるように、債権者にも配慮した計画を策定すべきです。
具体的には、会社が破産するよりも、民事再生の方が多くの額を回収できるようにすることがポイントとなります。
他方で、無理な返済計画だと実現可能性がないと判断されるため、実現可能な計画とすべきです。
POINT3資金繰りの問題を解決する
民事再生は、上記のとおり、申立から再生計画が認可されるまで、通常5ヶ月以上を要します。
その間、通常、信用取引は期待できず、現金決済を覚悟しなければなりません。
金融機関による融資もほぼ不可能なため、資金繰りの問題が浮上します。
この問題を解決するために、通常はスポンサーを探す必要があります。
したがって、民事再生を申立てる場合、事前にスポンサーについて検討しておくべきです。
民事再生に必要な費用とは?
民事再生は、通常、破産手続よりも高額な費用が必要となります。
民事再生に要する費用は、裁判所に納付する額(予納金)と申立ての代理人となる弁護士に支払う費用の合計となります。
裁判所に納める額
予納金とは、裁判所に納めなければならない金額のことをいいます。
予納金の額は、負債総額によって異なります。目安としては下表のようになります。
| 負債総額 | 予納金額 |
|---|---|
| 5千万円未満 | 200万円 |
| 5千万円~1億円未満 | 300万円 |
| 1億円~10億円未満 | 400万円(5億未満) 500万円(5億以上) |
| 10億円~50億円未満 | 600万円 |
| 50億円~100億円未満 | 700万円 |
| 100億円~250億円未満 | 900万円 |
| 250億円~500億円未満 | 1000万円 |
| 500億円~1000億円未満 | 1200万円 |
| 1000億円以上 | 1300万円 |
注 東京地裁の目安の基準となります。状況によって増減となる可能性があります。
民事再生の弁護士費用
民事再生をご依頼される場合の当事務所の弁護士費用は下表のとおりです。
| 着手金 | 予納金と同程度 |
|---|---|
| 預り金 | 予納金+10万円以上 |
| 報酬金 | 予納金の10分の1 |
※状況によって増額される場合があります。
弁護士費用の具体的な金額については、ご相談時にお見積をお出しいたしますので、お気軽にご相談ください。
民事再生のご相談について
民事再生については倒産・再生問題に関する専門的な知識・経験が必要となるため、当事務所では破産再生チームに所属する弁護士がサポートしております。
民事再生について、お気軽にご相談ください。
ご相談の流れはこちらのページをご覧ください。