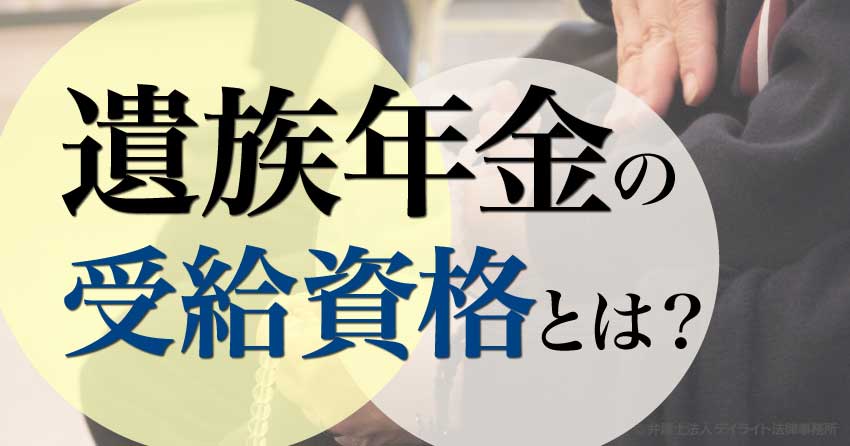
遺族年金の受給資格は、死亡した方に関する条件(保険料納付済期間の月数など)とご遺族に関する条件(配偶者・子などであること、亡くなった方に生計を維持されていたことなど)を満たす場合に得られます。
遺族年金の受給資格は、「家族が亡くなれば必ず認められる」というものではなく、一定の条件を満たしたご遺族のみに認められるのです。
この「受給資格を得るための条件」の中には、保険料納付済期間や亡くなった方と「生計を同じくしていた」ことのように、ご家族が生きている間でなければ満たすことのできないものもあります。
そのため、遺族年金の受給資格については、ご家族がまだ元気なうちから調べて、対応を進めておくことが大切です。
ここでは、遺族年金の受給資格を得るための条件、遺族年金の金額についてご紹介し、具体的なケースでの遺族年金額のシミュレーション、遺族年金の受給資格に関する注意点、相談窓口などについても取り上げていきます。
*なお、以下でご紹介する内容・金額は、令和7年7月時点で調査したものとなります。
目次
遺族年金の受給資格とは?
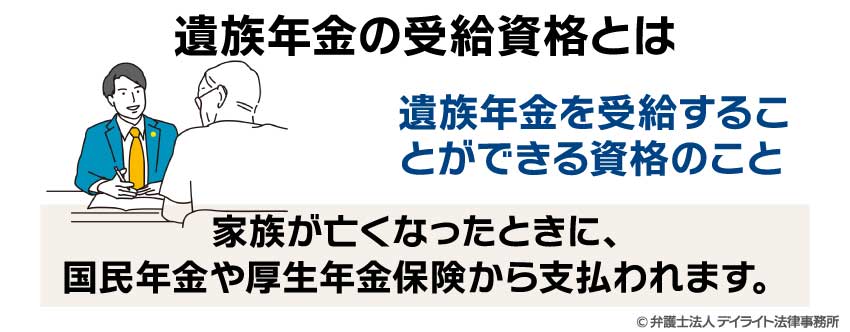
遺族年金の受給資格とは、遺族年金を受給することができる資格のことです。
遺族年金は、家族が亡くなったときに、国民年金や厚生年金保険から支払われます。
しかし、家族が亡くなったときに、常に遺族年金が支払われるとは限りません。
一定の条件を満たして受給資格を得られる場合でなければ、国民年金や厚生年金に加入して保険料を払っていても、遺族年金の受給はできないのです。
そもそも遺族年金とは?
遺族年金とは
遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入している(又は加入していた)人が亡くなったときに、残されたご遺族に支給される年金です。
家族がなくなると、その家族が担っていた役割を果たす人がいなくなってしまい、残された家族に経済的な影響が出る場合があります。
特に、一家の大黒柱のような稼ぎ手が亡くなってしまうと、遺族の生活が経済的に立ち行かなくなることもあります。
そのような苦境に立たされた遺族の生活を支えるため、国民年金・厚生年金から遺族年金が支給されることとなっているのです。
遺族年金の種類
遺族年金には、次の2種類があります。
- 国民年金保険から受給する遺族基礎年金
- 厚生年金から受給する遺族厚生年金
これら2つの年金は、受給資格も支払われる金額もそれぞれ異なります。
遺族年金に関する全般的な説明は、次のページで取り上げています。
遺族年金をもらえる条件
遺族年金をもらえる条件は、次の2種類に分けられます。
- 亡くなった方に関する条件
- ご遺族に関する条件
それぞれの条件について、ご紹介します。
亡くなった方に関する条件
亡くなった方については、国民年金、厚生年金に一定期間加入し、保険料を納付していた(又は保険料の免除を受けていた)ことなどが必要です。
どの程度の加入期間などが必要かは、遺族基礎年金と遺族厚生年金でそれぞれ内容が異なります。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金の場合、亡くなった方が次の①~④のいずれかに当てはまることが条件となります。
- ① 国民年金の被保険者である間に死亡した
- ② 国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡した
*①②の要件を満たして遺族基礎年金の受給資格を得る方については、
死亡する日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること
が必要になります。
ただし、死亡した日が令和18年3月末日までのときは、亡くなった人が65歳未満であれば、死亡する日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいこととされています。
- ③ 老齢基礎年金の受給権者だった方が死亡した
- ④ 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した
*③④の要件を満たして遺族基礎年金の受給資格を得る方については、
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上あること
が必要になります。
参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金の場合、亡くなった方が次の①~⑤のいずれかに当てはまることが条件となります。
- ① 厚生年金保険の被保険者である間に死亡した
- ② 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した
*①②の要件を満たして遺族年金の受給資格を得る方については、
死亡する日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること
が必要とされます。
ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡する日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいこととされています。
- ③ 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡した
- ④ 老齢厚生年金の受給権者だった方が死亡した
- ⑤ 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した
*④⑤の要件を満たして遺族年金の受給資格を得る方については、
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上あることが必要とされています。
参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
ご遺族に関する条件
遺族年金を受け取れるご遺族は、亡くなった方と一定の関係にあった方、亡くなった方に生計を維持されていた方に限られます。
どのような関係にあった方が遺族年金を受けられるかは、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれで異なります。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金の受給資格を有するご遺族は、次の方になります。
遺族基礎年金の受給資格を有する遺族
- 子のある配偶者
- 子
(いずれの場合も、亡くなった方に生計を維持されていたことが必要)
「子」は、以下のいずれかに当てはまる者に限られます(以下、この記事で「子」という場合は、以下の者を指す。)。
- 18歳になった年度の3月31日までにある
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の状態にある
以下のいずれかに当てはまる場合には、子には遺族基礎年金は支給されません。
- 子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている
- 子に生計を同じくする父又は母がいる
参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
上のとおり、遺族基礎年金の受給資格があるご遺族は、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」になります。
そのため、亡くなった方に「子」がない場合は、遺族基礎年金は支給されません。
ちなみに、亡くなった方の配偶者に連れ子がいたけれども、亡くなった方と養子縁組をしていないという場合は、その連れ子は、亡くなった方の「子」にはなりません。
また、「子のある配偶者」であっても「子」であっても、亡くなった方に生計を維持されていたことが必要になります。
どのような場合に「生計を維持されていた」と認められるかについては、後ほど解説します。
なお、「子のある配偶者」が遺族基礎年金を受給している間や、子に「生計を同じくする父又は母」がある間は、子は遺族年金を受給できません。
ただし、令和10年4月からは、「子のある配偶者」が遺族基礎年金を受けられない場合は、父又は母と生計を同じくしていても、「子」が遺族基礎年金を受給できるようになる予定です。
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金の受給資格を有する遺族は、死亡した人に生計を維持されていた次の遺族のうち、最も優先順位が高い遺族になります(①~⑥は優先順位の順に列挙。ただし、①と②は同順位となる)。
- ① 子のある配偶者
- ② 子
- ③ 子のない配偶者
- ④ 父母
- ⑤ 孫
- ⑥ 祖父母
- ① 子のある配偶者と②子は同順位となっていますが、子のある妻(母)又は子のある55歳以上の夫(父)が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金が支給されません。
一方、遺族である夫(父)が55歳未満の場合は、遺族厚生年金は子に支給されます。
なお、父母、祖父母については、55歳以上である方に限り受給できます(受給開始は60歳から)。
③子のない配偶者については、年齢・性別によって、受給資格・受給期間に違いがあります。
| 子のない配偶者の受給資格・受給期間は年齢・性別によって変わる | ||
|---|---|---|
| 子のない妻の場合 |
|
|
| 子のない夫の場合 |
|
|
子のない妻の場合、妻が30歳未満の時に夫と死別したのであれば、遺族厚生年金を受給できる期間は5年間に限られます。
妻が30歳以上になってから死別したのであれば、妻は、無期限で給付を受けられます。
一方、「子のない夫」は、死別当時55歳以上である場合に限り遺族厚生年金を受給できます(受給開始は60歳から。ただし、遺族基礎年金を合わせて受給できる場合に限って、55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受給できます。)。
参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
ただし、この点については、令和7年に法改正がありました。
この改正により、子がいない配偶者について、受給資格が次のように変更されています。
夫も妻も、配偶者と死別したのが60歳未満の場合、原則として支給期間を5年間に限る。
配偶者と死別したのが60歳以上の場合、無期限で遺族厚生年金を受給できる。
受給期間が5年に限られる給付については、収入要件(前年の年収・所得が一定の金額以下であることが必要との要件。詳しくは後述)が廃止され、収入の多寡にかかわらず、遺族厚生年金の受給が可能になる。
*5年を過ぎた場合も、障害状態にある、収入が十分でないなどの場合には、続けて遺族厚生年金を受給することができます。
上の改正は、子がいない配偶者に関するものですので、子がいる配偶者については、養育すべき子がいる間は、現行の制度が引き続き適用されます。
また、既に遺族厚生年金を受給している方には、この法改正は適用されません。
「生計を維持されていた」とは
遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給資格をもつのは、亡くなった方に「生計を維持されていた」遺族に限られます。
「生計を維持されていた」と認められるためには、
- 亡くなった方と生計を同じくしていたこと
- ご遺族が収入要件を満たしていること
が必要になります
収入要件を満たすには
収入要件を満たすには、「前年の収入が850万円未満、又は、前年の所得が655万5000円未満であること」が必要になります。
「生計を同じくしていた」と認められるには
亡くなった方と「生計を同じくしていた」と認められるのは、たとえば次のような場合です。
- 住民票上同一世帯に属しているとき
- 住民票上世帯を異にしているけれども、住所が住民票上同一であるとき
- 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
ア 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
イ 単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
- ① 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
- ② 定期的に音信、訪問が行われていること
ア 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
イ 生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき
参考:生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔厚生年金保険法〕(◆平成23年03月23日年発第323001号)
遺族年金を受給できる条件は、以下のページでも詳しくご紹介しています。
【参考】寡婦年金について
夫を亡くした妻(寡婦)のうち、夫が国民年金の第1号被保険者(例:自営業者)だった方には、寡婦年金が支給される場合があります。
寡婦年金の受給資格を得るためには、以下の「亡くなった方に関する条件」を全て満たす必要があります。
- 亡夫の国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間及び国民年金の保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間も含む)が10年以上あった(死亡日前日の時点)
*死亡日が平成29年7月31日以前の場合、25年以上の期間が必要 - 亡夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない
*死亡日が令和3年3月31日以前の場合、亡夫が障害基礎年金の受給権者だったとき、又は老齢基礎年金を受けたことがあるときは、寡婦年金は支給されない
寡婦年金の受給資格を得るための「ご遺族に関する条件」を満たすには、次の条件の全てを満たすことが必要になります。
- 夫と妻の婚姻関係が10年以上継続していた(事実上の婚姻関係も含まれる)
- 死亡当時、妻が夫に生計を維持されていた
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していない
寡婦年金が支給されるのは、上の条件を満たした妻が、60歳から65歳になるまでの間になります。
参考:寡婦年金|日本年金機構
遺族年金はいくらもらえる?
遺族年金の計算式
遺族年金の計算式は、遺族基礎年金と遺族厚生年金では全く異なります。
それぞれの計算式について、簡単にご紹介します。
遺族基礎年金の計算式
①配偶者が受給権者である場合
配偶者が受給権者の場合は、遺族基礎年金の計算式は次のようになります。
*昭和31年4月2日以前生まれの方が受給する場合は、2400円減額されます。
上の式にある「子の加算額」は、次のとおりとなっています。
- 1人目・2人目の子の場合 1人当たり23万9300円
- 3人目以降の子の場合 1人当たり7万9800円
なお、子の加算額については、令和7年の法改正により引き上げられ、何人目の子であっても、一人当たり一律28万1700円とされることになりました(施行は令和10年4月)。
②子が受給権者である場合
子が受給権者の場合、遺族基礎年金(子全員の合計額)は以下の計算式で計算されます(子1人当たりの遺族基礎年金は、以下の計算式で算出した金額を子の数で割った額となります)。
*子の加算額の金額は、配偶者が受給権者である場合と同額
参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
遺族厚生年金の計算式
遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3となります。
報酬比例部分の計算式は、次のA、Bの計算式により算出された各金額を足し合わせたものとするのが原則です。
A 平成15年3月以前の加入期間に関する部分
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
B 平成15年4月以降の加入期間に関する部分
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
ただし、亡くなった方が次の①~③のいずれかに基づいて遺族厚生年金を受給する場合は、厚生年金の被保険者期間が25年(300月)未満でも、25年(300月)とみなして報酬比例部分を計算します。
- ① 厚生年金保険の被保険者である間に死亡した
- ② 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した
- ③ 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡した
また、遺族厚生年金の受給権者が65歳以上で、自分の老齢厚生年金の受給権を有している場合は、配偶者が亡くなったことによって遺族厚生年金を受け取るときは、次の2つの額を比較し、高い額となる方を遺族厚生年金の額とします。
- 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
- 「亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額」と「自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額」を合算した額
参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
寡婦の場合の加算
妻が夫を亡くした場合、一定の条件を満たすと、以下の加算が受けられます。
- ①中高齢寡婦加算
- ②経過的寡婦加算
それぞれについて、ご紹介します。
①中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算を受けることができるのは、次の条件のどちらかを満たした場合です。
- ① 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない
- ② 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた「子のある妻」が、子が18歳に到達する年度の末日(3月31日)に達した(障害の状態にある場合には20歳に達した)等のため、遺族基礎年金をもらえなくなった(ただし、妻が40歳に到達した時に、子がいるために遺族基礎年金を受給していたことが必要)
*平成19年3月31日以前に夫が死亡し、遺族厚生年金を受給している場合は、①②の「40歳」を「35歳」と読み替える。
中高齢寡婦加算を受けられる期間は40歳から65歳までで、金額は62万3800円です。
なお、亡くなった夫が老齢厚生年金の受給権者の方又は受給資格期間を満たしていた方だった場合には、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(*)の場合に限り、中高齢寡婦加算を受けられます。
*中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方は、その期間
②経過的寡婦加算
経過的寡婦加算は、次のいずれかに該当する場合に、遺族厚生年金に加算して受給することができます。
- 昭和31年4月1日以前生まれの妻が、65歳以上になってから遺族厚生年金の受給権を得たとき
(亡くなった方が老齢厚生年金の受給権者又は受給資格を満たしていた方である場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(*)以上の場合に限る)
*中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方は、その期間 - 中高齢寡婦加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が、65歳に達したとき
経過的寡婦加算の金額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせて中高齢寡婦加算と同程度の額となるように決められています。
参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
【参考】寡婦年金の金額
寡婦年金は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3の額となります。
*保険料の全部又は一部の免除を受けていた期間がある場合は、計算方法が異なる。
参考:老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構
具体的には、次の表のとおりです。
| 加入期間 | 寡婦年金額 |
|---|---|
| 10年 | 約15万5000円 |
| 20年 | 約31万1000円 |
| 30年 | 約46万7000円 |
| 40年 | 約62万3000円 |
*上記の金額は、全期間の保険料を納付済みであることを前提としています。
寡婦年金が支給される期間は、妻が60歳から65歳になるまでの間のみとなります。
妻が60歳未満の時に夫が死亡した場合も寡婦年金は支給されますが、支給開始は、妻が60歳になってからとなります。
参考:寡婦年金|日本年金機構
遺族年金の受給額をシミュレーション
実際に受給できる遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の金額を、いくつかの具体例に基づいてシミュレーションしてみましょう。
*寡婦年金・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算については、ここでは取り上げていません。
夫が亡くなり、妻と子が残された場合
一家の生計を維持していた夫が亡くなって、妻と子が残された場合、妻が、遺族基礎年金と(夫が厚生年金に加入していれば)遺族厚生年金の両方を受け取ることになります。
この場合、遺族基礎年金額は、子どもの人数によって、以下に掲げる表のようになります。
| 子の人数 | 遺族基礎年金額 |
|---|---|
| 1人 | 107万1000円 |
| 2人 | 131万0300円 |
| 3人 | 139万0100円 |
| 4人 | 146万9900円 |
| 5人以上 | 子が一人増えるごとに7万9800円加算 |
遺族厚生年金の額は、亡くなった方の平均標準報酬額により、以下の表のようになります。
| 平均標準報酬額 | 遺族厚生年金額(目安) |
|---|---|
| 20万円 | 24万6645円 |
| 25万円 | 30万8306円 |
| 30万円 | 36万9968円 |
| 35万円 | 43万1629円 |
| 40万円 | 49万3290円 |
| 45万円 | 55万4951円 |
| 50万円 | 61万6613円 |
| 55万円 | 67万8274円 |
| 60万円 | 73万9935円 |
| 65万円(平均標準報酬額の上限) | 80万1596円 |
*上の表の遺族厚生年金額は、加入期間が平成15年4月以降300月、配偶者が40歳未満であることを前提としています。
*報酬月額63万5000円以上の場合、平均標準報酬額は65万円となります。
子がない夫婦の一方が亡くなった場合
子がない(又は、全ての子どもが既に、遺族年金上「子」と扱われる要件を満たさない年になった)夫婦の場合、遺族基礎年金の受給資格は得られません。
一方、遺族厚生年金については、要件を満たせば受給資格が得られます。
遺族厚生年金の額は、前の項で挙げた表をご参照ください。
子のみが遺族年金を受け取る場合
子のみが遺族年金を受け取る場合、遺族基礎年金と(亡くなった父又は母が加入していれば)遺族厚生年金を受給することができます。
遺族基礎年金の額は、下の表のとおりです。
| 子の人数 | 子全員分の遺族基礎年金総額 | 子1人当たりの遺族基礎年金 |
|---|---|---|
| 1人 | 83万1700円 | 83万1700円 |
| 2人 | 107万1000円 | 53万5500円 |
| 3人 | 115万0800円 | 38万3600円 |
| 4人 | 123万0600円 | 30万7650円 |
| 5人目以降 | 子の人数が1人増えるごとに、7万9800円ずつ上がる | |
なお、既にご説明したとおり、令和10年4月からは、子の加算額が増額される予定です。
遺族厚生年金の金額は、前々項でご紹介した表のとおりです。
遺族年金の受給資格の注意点
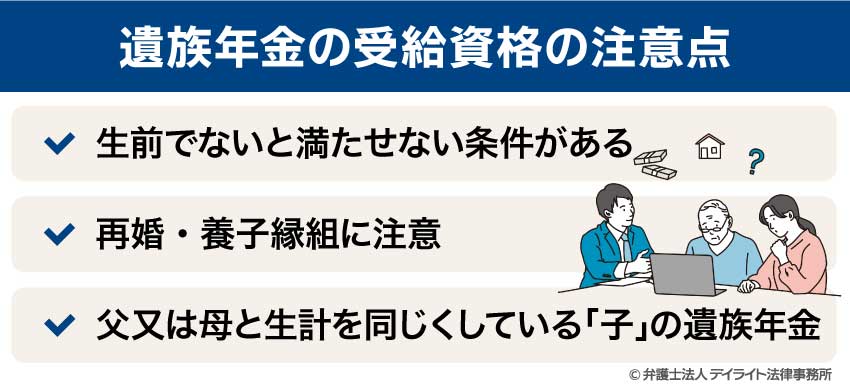
生前でないと満たせない条件がある
遺族年金の受給資格を得るための条件の中には、以下のように、生前でなければ満たすことができないものがあります。
- 「生計を同じくしていた」と認められるための、同居、住民票の移転、経済的援助、定期的な音信・訪問などを行う(一方の配偶者が施設に入っている場合なども注意が必要)
- 保険料の免除申請をする
- 厚生年金保険に加入するために仕事を始める
- (配偶者の連れ子などと)養子縁組を行う
こうした対策は、ご本人が亡くなった後では行えませんので、ご家族が生きているうちから、社会保険労務士に相談するなどして、遺族年金の受給資格を得るための対策を始めておくことをおすすめします。
再婚・養子縁組に注意
遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給している方が、結婚をした(内縁関係も含む)、直系親族、直系姻族以外の人の養子になった、ということになると、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給資格を失ってしまいます。
遺族基礎年金を受け取っている場合、「子」の結婚なども、遺族基礎年金の受給資格に影響を与えます。
「子」の全員が、
- 結婚した
- 受給権者以外(父又は母)以外の人の養子になった(親の再婚相手との養子縁組など)
- 亡くなった人(父又は母)と離縁した
という場合、「子のある配偶者」も、遺族基礎年金を受けることができなくなるのです。
父又は母と生計を同じくしている「子」の遺族年金
「子」は、父又は母と生計を同じくしている場合、遺族基礎年金の受給資格を得られません。
そのため、親子で同居しているなど生計を同一にしていると、次のような場合に、親子ともに遺族年金を受けられなくなってしまいます。
- 父又は母が再婚した
- 父又は母の収入が収入要件を満たさない
- 生前の父母が離婚しており、子を養育していた父(又は母)が亡くなった後、元配偶者である母(又は父)が子を引き取った
なお、この点については法改正があり、父又は母と生計を同じくしていても、父又は母が遺族基礎年金を受け取れない場合は、子が遺族基礎年金を受け取れるようになります(施行は令和10年4月から)。
遺族年金の受給資格についての相談窓口
遺族年金の受給資格について相談できる窓口としては、次のようなものがあります。
- 社会保険労務士
- 各地の年金事務所
- 街角の年金相談センター(日本年金機構から全国社会保険労務士連合会に委託して運営しているもの)
- ねんきんダイヤル(日本年金機構)
- 国家公務員共済組合連合会
- 地方公務員共済組合連合会
- 日本私立学校振興・共済事業団 私学共済事業
- 市区町村役場
相続については弁護士
遺族年金の受給資格が気になる方の中には、同じくご家族の亡くなった後に問題となる相続についても関心がおありの方もおられるでしょう。
相続に関するご相談は、相続に強い弁護士までご相談下さい。
相続に強い弁護士ならば、他の専門家等と異なり、遺産分割についての交渉、相続の放棄、調停・訴訟の手続、登記、相続税の問題などといった相続全般の問題に対応することができます。
さらに、相続についての問題を弁護士に相談、依頼することには、次のようなメリットもあります。
- 相続の専門知識をもった弁護士からアドバイスを受けられる
- 親族との交渉が必要になったときに、弁護士に窓口になってもらうことができ、感情的な対立を避けやすくなる
- 法的な手続きが必要になった場合にも適切に対処してくれる
- 手間のかかる戸籍の取得なども代わりに行ってくれる
- 法的な根拠をもって遺産分割を進めることができるので、関係者が納得できる場合が多くなる
相続に強い弁護士に相談することのメリット、相続に強い弁護士に相談することが望ましいケース、相続に強い弁護士を選ぶ際のポイントに関しては、以下のページで詳しくご紹介しています。
遺族年金の受給資格についてのQ&A
![]()
遺族年金がもらえないケースってどんなとき?
- 亡くなった方の保険料納付済期間、保険料免除期間、国民年金加入期間などが足りない
- 亡くなった方に「子」(養子を含む)がいない(遺族基礎年金の場合)
*配偶者の連れ子は、亡くなった方と養子縁組をしていない限り、「子」に当たらない
- ご遺族の収入が高く、収入要件を満たさない
- 亡くなった方とご遺族が同居しておらず、仕送り、定期的な音信などもなかった
*亡くなった方又はご遺族が入院・入所している場合も、同居していないとされる可能性がある。
遺族年金をもらえる条件については、次のページもご一読ください。
![]()
遺族年金と自分の年金は両方もらえますか?
そのため、どちらかを選択する必要があります。
ご遺族が厚生老齢年金を受け取ることができる場合は、ご自分の国民年金(老齢基礎年金)と厚生老齢年金だけでなく、ご自身の厚生老齢年金額を超える部分の遺族厚生年金を受給することができます。
参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
![]()
夫が死んだ場合、妻はいつまで遺族年金をもらえる?
- ① 子が18歳になった年度の3月31日になるまで(子に障害年金の障害等級1級又は2級の障害がある場合は、20歳になるまで)
- ② 妻が死亡したとき
- ③ 妻が結婚したとき(内縁関係になったときを含む)
- ④ 妻が直系血族又は直系姻族以外の人の養子になったとき
- ⑤ 子全員が死亡したとき
- ⑥ 子全員が結婚したとき(内縁関係になったときを含む)
- ⑦ 子全員が妻以外の人の養子になったとき
- ⑧ 子全員が死亡した夫と離縁したとき
- ⑨ 子全員が妻と生計を同じくしなくなったとき
一方、遺族厚生年金については、子の年齢に関係なく、次のときまでは、受給し続けることができます。
- ① 妻が亡くなったとき
- ② 妻が結婚したとき(内縁関係も含む)
- ③ 妻が直系血族又は直系姻族以外の人の養子となったとき
- ④ 夫の死亡時に妻が30歳未満の「子のない妻」だった場合、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年経過したとき(*)
- ⑤ 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給していた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利を失い、その権利を失ってから5年を経過したとき(*)
(*)平成19年4月1日以降に夫が亡くなり、遺族厚生年金を受け取ることとなった場合に限る。
参考:遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき|日本年金機構
まとめ
ここまで、遺族年金の受給資格について解説しました。
遺族年金の受給資格を得るためには、ご家族がご存命のうちから対策をとっておかなければならない場合があります。
遺族年金の受給資格については、早いうちから各種相談窓口や社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。
また、ご家族が亡くなられたときには、相続に関する問題も出てきます。
相続に関する問題も、なるべくご生前から、相続に強い弁護士を探して相談し、遺言書の作成、家族との話し合いなどによる対策を行っておくおことをおすすめします。
当事務所においては、相続問題を集中して取り扱う弁護士による相続対策チームを設け、相続についてのお悩みをお持ちの方からのご相談を全般的にお受けしております。
全国からの電話・オンラインを通じたご相談もお受けしております。
相続に関する問題については、ぜひ一度お気軽に、当事務所までご相談ください。

