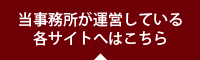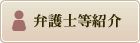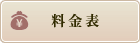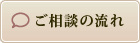略式起訴とは?前科や罰金相場をわかりやすく解説

略式起訴とは、正式な裁判は開かれず、検察官から提出された書面でのみ審理される起訴方法です。
100万円以下の罰金刑もしくは科料のみの刑罰を言い渡す特別な裁判手続になります。
このページでは、略式起訴と通常の起訴との違いや、メリット・デメリット、手続きの流れなどについて弁護士が詳しく解説いたします。
略式起訴とは
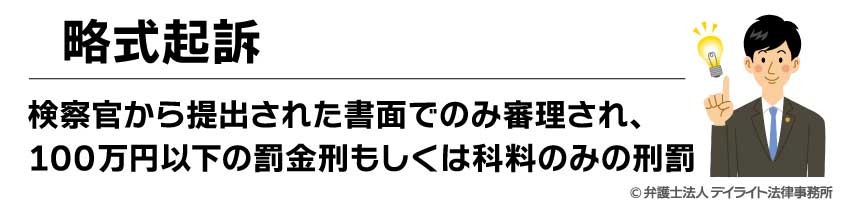
略式起訴とは、検察官が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面での審理のみで罰金もしくは科料の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることです。
略式起訴と通常の起訴との違い
通常の起訴(正式起訴)とは、「公判請求」とも呼ばれ、裁判所、すなわち公開の法廷における正式な裁判(「公判」といいます)を開くよう求めることです。
通常の起訴による正式裁判と略式起訴による処分決定の違いは、以下のとおりになります。
| 通常の起訴による正式裁判 | 略式起訴による処分決定 | |
|---|---|---|
| 場所 | 裁判所(公開の法廷)に当事者が出廷する | 正式な裁判は開かれない(出廷なし) |
| 審理 | 書証に加え、被告人質問・証人尋問など、口頭で話したことも証拠として扱われる | 当事者が意見を述べる機会はなく、検察官から提出された書面でのみ審理される |
| 刑罰 | 拘禁刑など罰金刑以外の処分があり得る | 100万円以下の罰金刑もしくは科料のみ |
対面か書面かで審理の方法が違う
検察官が通常どおり起訴した場合、公開の法廷において正式な裁判を行うことになります。
この場合は当然ながら、起訴された被告人は裁判に出席しなければなりません。
そして、裁判の中では、検察官は捜査機関が収集した証拠に基づき罪の成立を主張する一方、被告人側からも証拠を提出し、無実を主張するか、もしくは情状酌量を求めていくことになります。
これに対し、略式起訴の場合、弁護側が証拠を提出することはありません。
裁判所は、検察官が提出した証拠のみに基づき、最終的な処分を決定するのです。
被告人の権利放棄の違い
我が国においては、全ての国民は、3回まで裁判を受けることが認められています。
公開の法廷において、双方の主張をぶつけ、裁判官にその判断を委ねる機会が保障されているのです。
しかし、略式起訴がされた場合、被告人が自身の主張を行う場は用意されません。
すなわち、公開の法廷において裁判を受ける権利を放棄するということになります。
略式起訴はいつどのような要件で決まる?
略式起訴はいつ決まる?
略式起訴をされるまでの流れは以下のようなイメージで行われます。
-
- 1
- 警察が事件処理に必要な捜査を行い、証拠収集を行う
(1か月から2か月程度)
-
- 2
- 内容検察庁に送致される(俗に言う「書類送検」)
(数日程度)
-
- 3
- 検察官が事件記録を読んで処分を考える
(1か月から3か月程度)
-
- 4
- 検察官から呼び出されて略式起訴に関する説明を受け、被疑者が同意する
略式起訴を行うかどうかを決めるのは、検察官です。
検察官が略式起訴をするかどうか決めるのは、警察から取り調べなどの捜査を受け、検察官へ事件が送致されてからになります。
事件全体の流れからすると一番最後に決まるというイメージです。
略式起訴の要件
本来、刑事裁判は公開の法廷で行われることが予定されており、公開の法廷で被告人も色々な主張を行うものです。
しかし、全ての事件について公開の法廷で裁判を行うと、検察官や裁判所も大変です。
また、公開の法廷で自分が起こした事件の内容や自分の情報について話すことに抵抗があるという人も少なくありません。
そのため、関係者の利害が一致している場合には簡単な手続きで裁判を終わらせようという考えから、一定の要件のもと、略式起訴というものが認められています。
具体的な要件は、以下のとおりです。
- ① 簡易裁判所の管轄に属する事件であること
- ② 100万円以下の罰金又は科料が相当な事件であること
- ③ 被疑者が略式起訴に同意すること(事件を争わないこと)
裁判所や検察庁、処罰を受ける犯人が早く事件を終わらせたいと考えたとしても、重い罪を犯した場合まで略式起訴を認めると、国民から見て司法の判断が不透明になってしまいます。
そのため、あくまでも軽微な事件に限定するために、簡易裁判所の管轄に属する事件であり、100万円以下の罰金又は科料が相当な事件であることが必要とされています。
また、略式起訴をされた場合、書面のやり取りだけで手続きが終わってしまいますから、被疑者が犯行を認めていないような事件では不適切ということになります。
そのため、略式起訴は、被疑事実を全て認めていて、被疑者が自らの行為について争わないことが明らかであり、「公開の法廷で裁判を受けなくても良いので簡略化された手続で罰金を支払い、早く終わらせて欲しい」という被疑者の同意を得て初めて可能になるのです。
略式起訴のメリットとデメリット
略式起訴のメリットとデメリットは、以下のとおりになります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
最大のメリットは、裁判に出席する負担を回避できるという点になるといえます。
裁判を行う場合、簡易な事件であったとしても、起訴されてから第1回の裁判が開かれるまでに1ヶ月以上の期間が空いてしまうことがほとんどです(複雑な事件の場合、さらに長引く可能性があります)。
また、1回目の裁判で判決の言い渡しまでなされるケースもありますが、多くの場合は2回以上の出廷が必要になります。
裁判は平日の日中にしか開かれませんので、裁判のために仕事を休まなければならないことが増えると、それだけ負担も大きくなるといえるでしょう。
他方で、公開の法廷における審理を受けることを放棄してしまうと、上記のようなデメリットもあります。
裁判に行かずに済む上に迅速な解決にもつながる、というメリットだけに目を向けるのではなく、略式起訴を選択しても本当に問題がないかどうか、よく考えて決断する必要があります。
略式命令の確率
令和6年度の犯罪白書によれば、令和5年における検察庁が最終的な処分を決定した人数(終局処理人員総数)は79万1457人であり、このうち公判請求されたのは7万5384人(全体の9.5%)でした。
これに対し、略式起訴を行なったのは16万2761人(全体の20.6%)であり、公判請求された事件の倍以上の件数が、略式起訴により終結しているということになります。

略式起訴は会社にバレる?
結論として、略式起訴をされたとしても、そのことが会社にバレる可能性はほぼ無いと言っていいでしょう。
略式起訴がされた場合、書類のやり取りだけで裁判の手続きが終わることになります。
裁判所が罰金額を決定した後は、まず裁判所から「略式命令謄本」が届きます。
その後、1〜2週間ほどすると、今度は検察庁から「納付告知書」が届きます。
この納付告知書にしたがって罰金を納めれば、無事に手続きは全て終了となります。
会社に対して、検察庁や裁判所から連絡がいくようなことはありませんから、略式起訴による罰金刑を受けた事実を他人に知られることはまずありません。
詳しくは以下のページもご覧ください。
略式起訴に執行猶予はつく?
執行猶予は「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」につけることができるとされています(刑法第25条1項柱書)。
引用:刑法|e-Gov法令検索
そうすると、略式起訴をされる場合でも50万円以下の罰金刑とされれば、法律上は執行猶予をつけることも可能ということになります。
しかし、実務上は略式起訴で執行猶予がつくことはまずありません。
略式起訴となった場合には確実に罰金を支払わなければならないと考えておくべきでしょう。
略式起訴の手続きの流れ
 略式起訴を行うかどうかは、検察官が判断することになります。
略式起訴を行うかどうかは、検察官が判断することになります。
検察官による取調べの後、略式起訴による事件処理が相当であると判断された場合、検察官から被疑者に対し、略式起訴について説明を行います。
その上で、略式起訴を行うことについての同意書に署名押印をするよう促します。
被疑者本人が略式起訴による事件処理に同意し、同意書に署名・押印を行うと、検察官は簡易裁判所に対し、略式起訴の請求を行います。
簡易裁判所の裁判官が略式起訴を認めれば、被疑者に対し、略式命令が下されることになります。
略式起訴の不服がある場合
略式起訴され、罰金刑が言い渡されたものの不服があるという場合、略式命令の通知を受けた日から14日以内に、通常の裁判を受けることを請求することができます(刑事訴訟法465条)。
請求により正式な裁判が開かれ、判決が言い渡されると、略式命令はその効力を失うことになります(刑事訴訟法469条)。
引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口
略式起訴のよくあるご相談
![]()
略式起訴は前科がつく?
略式起訴をされた場合は、有罪判決が下され、100万円以下の罰金又は科料の刑事罰を受けることになります。
罰金の位置付けがピンとこないという方もよくいらっしゃいますが、このように罰金も立派な刑事罰であり、有罪判決を受けたことに変わりありません。
したがって、略式起訴を受けた場合には前科がつくということになります。
![]()
罰金を払えない場合どうすればいい?
労役場は刑務所とは違いますが、自由が制限された状況下で強制的に労働させられることになります。
そしてこの強制労働は、1日5000円という換算で罰金額に達するまで続きます。
もっとも、労役場行きを避ける方法が全く無いわけではありません。
罰金は一括での支払いが当然ですが、まずは検察庁に連絡して分割払いや支払期限伸長などの相談をしてみてください。
安定した収入を得ていて、分割で確実に支払いができる事情などが認められれば、要望が通るかもしれません。
![]()
公務員が略式起訴された場合の処分はどうなる?
参考:国家公務員法 | e-Gov法令検索
参考:地方公務員法 | e-Gov法令検索
他方、略式起訴された場合に受ける刑事罰は罰金刑や科料ですから、当然に失職することはありません。
しかし、法律に従って当然失職するわけではないとしても、懲戒処分によって失職するリスクはあります。
各所で公務員の懲戒処分基準が定められており、一定の犯罪を行った場合には免職もありうるとされていることが一般的です。
例として、東京都教育委員会において定められている懲戒処分の基準では、窃盗や痴漢等のわいせつ行為などを行った場合に免職がありうるとされています。
公務員が略式起訴された場合について、詳しくは以下のページもご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
略式起訴による処理は、罪を認め、早期の社会復帰を果たすことを考えるのであれば、メリットは大きいといえます。
その反面、裁判において自らの主張を行う機会を放棄するということにもつながりますので、略式起訴での処分を受け入れるかどうかについては、慎重に検討すべきです。
取調べを受けておられるなど、ご不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度刑事事件に注力する弁護士に相談されることをお勧めします。
その他のよくある相談Q&A
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか