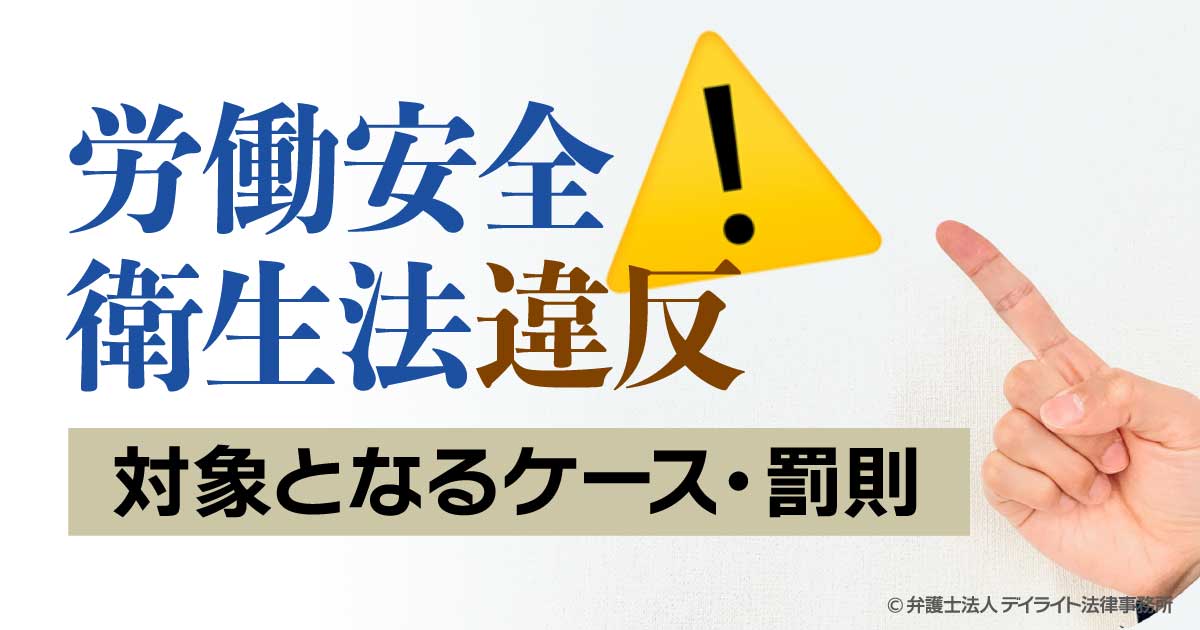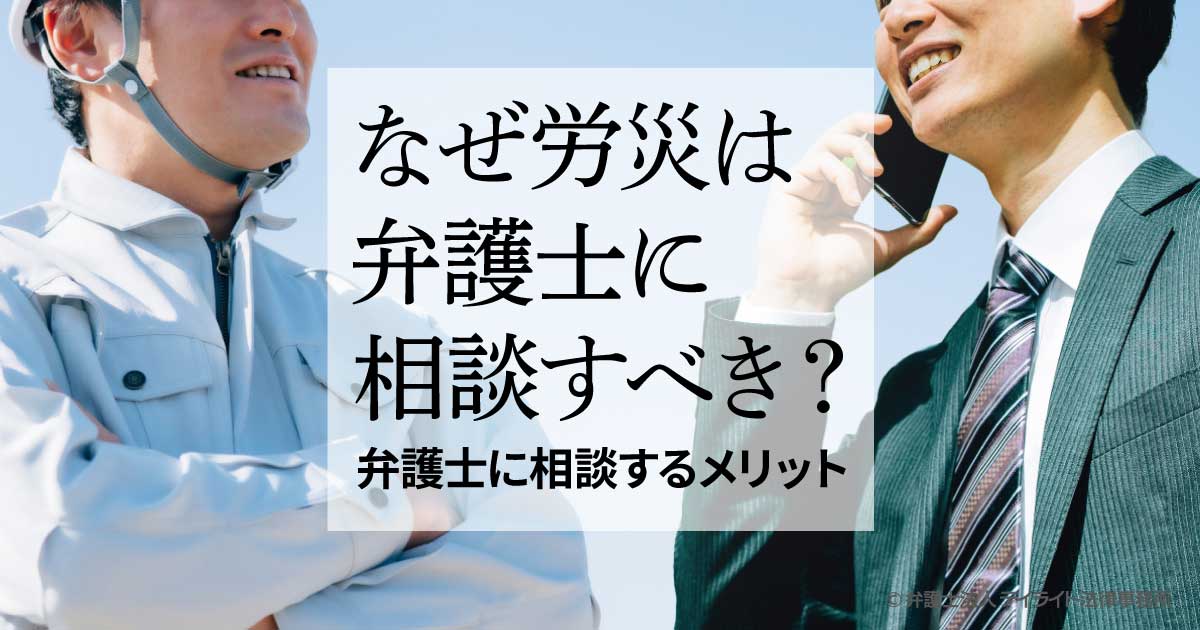弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

安全配慮義務とは、会社が従業員の生命、身体、健康を守るために必要な配慮をする義務のことをいいます。
会社には、こうした安全配慮義務が法律上課されています。
これは単なるモラルや企業倫理の問題ではなく、労働契約法に基づく明確な「法的義務」です。
会社がこの義務を怠った結果、従業員が怪我や病気を負えば、会社はさまざまな責任を問われることとなります。
中には、損害賠償請求や労災の認定にまで発展するケースも少なくありません。
安全配慮義務の具体的な内容は、単に事故やケガを防ぐといったものにとどまらず、適切な労働時間の管理や、職場内での人間関係への配慮、健康診断の実施・フォローアップといった広範かつ継続的な配慮が求められます。
つまり、会社には、従業員が安心して働ける環境を整えるための、総合的な取り組みを日常的に実施する責任があるのです。
この記事では、安全配慮義務の基本的な定義から法律上の根拠、過去の違反事例、違反した場合に会社が負う法的責任、安全配慮義務を果たすために会社がとるべき対策までを、法律の専門家の視点からわかりやすく解説します。
従業員として「この職場は大丈夫?」と不安を抱えている方はもちろん、人事担当者や経営者の方も知っておくべき重要な内容です。
職場の安全と健康に関わる法的リスクを未然に防ぐために、ぜひ最後までご一読ください。
目次
安全配慮義務とは?
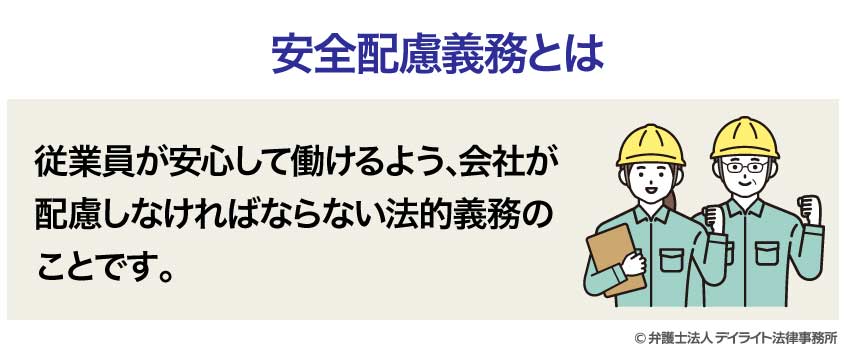
従業員が安心して働けるよう、会社が配慮しなければならない法的義務のことを「安全配慮義務」といいます。
もっとわかりやすく言えば、「従業員が怪我や病気をせず、心身ともに健康な状態で働けるように、職場環境や労働条件を整える責任が会社にある」ということです。
例えば、高所での作業をさせるのであれば安全帯などの適切な道具を用意する必要があります。
また、長時間労働の防止、ハラスメントが発生しない職場体制の構築なども、この安全配慮義務に含まれます。
安全配慮義務の法律の根拠
安全配慮義務の法的根拠は、労働契約法第5条です。
この条文により、使用者(=会社)は、従業員の命や健康を守るための配慮を行うことが法律上の義務であると明確にされています。
安全配慮義務の内容
安全配慮義務とは、会社が労働契約に基づき、従業員の生命や健康を守るよう配慮すべき義務のことです。
安全配慮義務は、大きく分けて「健康配慮義務」と「職場環境配慮義務」の2つの側面があり、それぞれが密接に関連しながら従業員の安全と健康を支える役割を果たしています
健康配慮義務とは、従業員が健康な状態で働けるように配慮する義務のことです。
具体的には、長時間労働や過度な心理的負荷が従業員の心身に悪影響を及ぼさないよう、業務量や勤務体制を調整するといった責任のことを指します。
例えば、長時間労働を回避する勤務シフトの整備、メンタルヘルスに配慮したカウンセリング体制の導入、定期的な健康状態のチェックなどが挙げられます。
職場環境配慮義務とは、従業員が安全に働ける環境を整備するように配慮する義務のことです。
具体的には、安全な設備の設置、作業マニュアルの整備、危険のある作業には適切な保護具を提供するなど、事故や健康被害を防ぐための対策を講じることが求められます。
また、快適な人間関係を保つための措置や、安心して働ける職場づくりといった観点も含まれます。
特に、パワハラやセクハラなどのハラスメントは、職場環境の整備という観点では「職場環境配慮義務」に該当し、同時に従業員の心身の健康を守るという観点では「健康配慮義務」にも関係する、非常に重要な問題です。
こうした健康と職場環境の両面からの配慮は、従業員が安心して長く働ける職場づくりの基本であり、会社にとっても持続可能な成長を実現するうえで不可欠な取り組みです。
会社には安全配慮義務を継続的に見直し、改善していくことが強く求められています。
会社が安全配慮義務を果たせていない兆候とは?チェックポイント
安全配慮義務は、従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮することを会社に求める法的義務です。
しかし、実際にはこの義務が十分に果たされていない職場も存在します。
ここでは、安全配慮義務が適切に履行されていない可能性がある職場の兆候や、注意すべきポイントを詳しく解説します。
- 危険な作業環境が改善されない
- 教育や研修の不足
- 相談への対応が遅い・形だけである
- 長時間労働が常態化している
- 有給休暇が取得しづらい雰囲気がある
- ハラスメントの訴えが軽視されている
- 健康診断が未実施、または異常値が放置されている
危険な作業環境が改善されない
ヒヤリ・ハットや軽微な事故が頻発しているにもかかわらず、安全対策の見直しや保護具の支給が行われていない場合、その職場では安全管理が不十分である可能性があります。
こうした状況が放置されていると、将来的に重大な事故や怪我が発生するおそれがあり、従業員の安全を守るために企業が負うべき配慮が十分に果たされていない兆候といえるでしょう。
教育や研修の不足
本来、業務の危険性について十分に理解するためには、定期的な安全教育や研修が欠かせません。
しかし、形だけで内容が乏しい研修しか行われていない場合、事故やトラブルの予防が難しくなります。
従業員の安全を確保するうえで必要な知識や意識が十分に共有されていない職場は、安全配慮義務が軽視されている可能性があります。
相談への対応が遅い・形だけである
不調や業務上の問題について従業員からの申告があっても、「聞くだけ」で終わり、実際の改善行動が取られていない場合、従業員の信頼を損ねるばかりか、健康被害が顕在化する恐れもあります。
こうした対応の姿勢が続いている職場では、安全配慮義務が十分に履行されていない可能性があります。
長時間労働が常態化している
時間外労働が常態化している職場では、従業員の疲労が蓄積し、心身の不調や労働災害のリスクが高まります。
特に、時間外労働が月80時間を超えるような状況は「過労死ライン」とされており、健康被害を引き起こす可能性があります。
こうした働き方が改善されていない職場は、安全配慮義務を果たせていない兆候といえるでしょう。
有給休暇が取得しづらい雰囲気がある
従業員には、法律により有給休暇を取得する権利が保障されています。
しかし、職場の雰囲気や制度上の問題から、実際には有給休暇を取りづらいケースも少なくありません。
このような状況が続くと、従業員が十分な休養を確保できず、体調不良やモチベーション低下を招く可能性があります。
有給取得がしにくい環境は、適切な労働環境が整っていないサインかもしれません。
ハラスメントの訴えが軽視されている
パワハラやセクハラなどの被害が報告されても、適切な対応がされていない場合、従業員は不安やストレスを抱えながら働くことになります。
これは、職場の安心・安全な環境が確保されていない状態といえ、企業の安全配慮義務の不足が疑われます。
健康診断の未実施・フォローがない
定期健康診断が実施されていない、あるいは異常所見が見つかっても再検査や必要な就業配慮を行わずに放置している場合、健康被害が深刻化するおそれがあります。
こうした状況は、企業が従業員の健康を守る責任を十分に果たしていないサインといえるでしょう。
安全配慮義務に違反した事例
会社に安全配慮義務違反が認められると判断された裁判例を3つご紹介します。
運送会社に勤務するトラック運転手が荷卸し作業中に腰に激痛を感じ受診したところ、腰椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄と診断され、最終的に労災等級9級7の2の後遺障害が残った事例
【会社の安全配慮義務】
会社には、従業員が肉体的に過度な負担を受けないように、作業に台車などの補助具を用意する、作業姿勢や動作について適切に指導する、作業量や時間を実態に応じて調整する、十分な休息を取らせるといった配慮をすべき義務があった。
判例 川義事件(最高裁昭和59年4月10日判決)
会社が従業員1人に対し24時間の宿直勤務を命じたところ、宿直中に強盗が侵入し、従業員が殺害された事例
【会社の安全配慮義務】
会社は、宿直中の従業員が外部からの侵入者によって危害を受けないよう、侵入を防ぐ設備を整えるか、設備が不十分な場合には宿直者を増やす、安全教育を行うなどの対策を講じる義務があった
判例 電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)
長時間労働が常態化していた中、配属後まもなく深夜帰宅や徹夜勤務が続いていた若手社員がうつ病を発症し、自宅で自殺した事例
【会社の安全配慮義務】
会社には、従業員に業務を割り当てて管理する際、業務に伴う疲労や精神的負荷が過度に蓄積し、従業員の心身の健康を損なうことのないよう適切に配慮すべき義務があった
安全配慮義務に違反した会社のペナルティ
会社が従業員の安全配慮義務を怠った場合、法的責任を問われることはもちろん、企業の信用や経営にも重大な影響が及ぶ可能性があります。
ここからは、安全配慮義務に違反した場合に生じる主なペナルティについて、刑事・行政・民事の3つの観点から解説します。
安全配慮義務に違反したときの罰則
会社が安全配慮義務に違反したとき、法的な制裁が科されることがあります。
ここでは、刑事・行政それぞれの責任について解説します。
刑事上の責任
会社が安全配慮義務を怠った結果、従業員が死亡したり重傷を負った場合、労働安全衛生法違反として会社やその代表者に罰則が課せられることがあります。
具体的には、労働安全衛生法第119条に基づき、会社やその代表者が「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されることがあります。
さらに、従業員の死傷が業務上の過失によるものであると認定された場合には、刑法211条の「業務上過失致死傷罪」に問われ、最大で「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科されることもあります。
労働安全衛生法違反となるケースと罰則については、以下の記事でも詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。
行政上の責任
安全配慮義務に違反した事案では、労働基準監督署による是正勧告や行政指導が行われることがあります。
重大な違反がある場合は、現場への立ち入り調査の上、改善命令が下されることも考えられます。
また、改善が見られない場合や悪質性が高いと判断された場合には、企業名の公表や事業停止命令など、企業活動に大きな影響を及ぼす行政処分が科されるケースもありますので、注意が必要です。
安全配慮義務違反による損害賠償
安全配慮義務に違反し、従業員が心身の不調や怪我・病気を発症した場合、企業は民事上の損害賠償責任を負うことになります。
このような損害賠償請求は、主に以下の2つの法的根拠に基づいて行われます。
- 債務不履行責任(民法第415条)
会社が雇用契約に基づいて負っている安全配慮義務を履行しなかった場合に適用されます。 - 使用者責任(民法第715条)
会社の業務を遂行するために使用している者(例:管理職など)が、業務上不法行為を行って他人に損害を与えた場合に適用されます。
引用元:民法|e−GOV法令検索
損害賠償の対象となる費目は、入通院費や治療費に加え、仕事を休まざるを得なかった期間の休業損害、さらに後遺障害が残った場合には将来の収入減少に対する逸失利益も含まれます。
これに加え、心身に与えられた精神的苦痛に対しては慰謝料の支払いも求められることになります。
損害賠償金の金額は事案の内容や被害の程度によって異なりますが、過去の判例では、数百万円から数千万円に達する高額な請求が認められた例も少なくありません。
特に、安全配慮義務違反が重大な健康被害や長期の労働不能に直結した場合には、会社に対して重い責任が課せられる傾向にあります。
会社が安全配慮義務違反をした場合に問われる民事上の責任については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ合わせてお読みください。
安全配慮義務違反による企業イメージの低下
法的責任だけでなく、企業イメージへの影響も無視できません。
労災事故や過労死、自殺といった深刻な事案が報道されると、企業のブランドや社会的信用にも大きなダメージを与えます。
結果として、取引先の信頼を失ったり、採用活動に悪影響を及ぼしたりするなど、企業の経営全体に長期的なダメージを与える可能性もあります。
昨今はSNS等を通じた情報拡散も早いため、安全配慮義務違反が明るみに出た際の影響はより深刻化しています。
企業が安全配慮義務を果たすことは、従業員の生命・身体の安全を守るだけでなく、企業自身の法的リスクや社会的信用を守るためにも極めて重要です。
安全配慮義務を果たすための会社の対策
安全配慮義務は、単に事故を防ぐだけでなく、長時間労働やハラスメント、メンタルヘルスなど現代的な課題にも対応することが求められます。
ここからは、安全配慮義務を果たすための会社の対策について、以下の6つの項目に分けて解説していきます。

職場環境の整備
従業員が安全かつ快適に働けるよう、物理的な職場環境を整えることは安全配慮義務の基本です。
具体的には、照明・換気・温度管理のほか、転倒や感電を防ぐための動線の確保、機械の安全装置の設置などが挙げられます。
また、有害物質を取り扱う職場では、保護具の支給や排気設備の整備も求められます。
労働時間の適正管理
長時間労働は、過労死やメンタル不調の大きな原因となるため、勤務時間を適切に管理することも安全配慮義務の重要な要素です。
労働基準法に基づき、法定労働時間・休憩・休日のルールを守ることはもちろん、時間外労働を行わせる場合にはいわゆる「36協定」の締結と届出が必要です。
また、36協定を締結していたとしても、厚生労働省が労災認定基準として示す「過労死ライン」(月80時間超の時間外労働など)を超えないように注意しなければなりません。
会社が従業員を法定時間を超えて働かせる場合に、会社と従業員の間で結ぶ協定のことです。
これを労働基準監督署に届け出ることで、時間外労働や休日労働が可能になります。
教育によるリスク予防策の実施
労働災害(労災)や健康被害を防ぐためには、従業員が正しい知識を持つことも重要です。
会社には、「雇入れ時」や「作業内容の変更時」などのタイミングで、従業員に対して安全や衛生に関する教育を行う義務があります(労働安全衛生法第59条)。
教育の内容としては、業務に必要な機械の使い方、災害時の対応、危険物の取り扱いなど、職場の特性に応じたものが求められます。
メンタルヘルス対策
近年、職場でのうつ病やストレス障害などの精神的な健康問題が深刻化しており、メンタル面への配慮も安全配慮義務の重要な一部となってきています。
とくに、従業員50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務化されています。
加えて、社内相談窓口の設置や、産業医との連携体制の整備など、メンタル面での支援体制を構築することが求められます。
ハラスメント対策と相談体制の整備
パワハラ・セクハラ・マタハラなどのハラスメントを未然に防ぎ、万が一発生した場合に適切に対応できる体制を整えることも、安全配慮義務の一環です。
2020年に改正されたパワハラ防止法(労働施策総合推進法)により、2022年4月からは中小企業も含めた全ての企業に防止措置を講じる義務が課されています。
具体的には、相談窓口の設置、再発防止策、被害者・加害者への対応などを適切に行う必要があります。
健康診断・産業医による健康管理
従業員の身体的健康を維持するために、会社は定期健康診断の実施とその結果に基づいた適切な対応を行う必要があります。
労働安全衛生法により、常時使用する従業員には年1回の定期健康診断を受けさせることが義務づけられています。
また、従業員数50人以上の事業場では産業医の選任も必須です。
健康診断等で異常が見つかった場合には、就業制限や業務内容の見直し、再検査の指示など個別対応も含めた適切な措置が求められます。
安全配慮義務の相談窓口
職場での安全配慮義務が十分に果たされていないと感じたとき、どこに相談すればよいのか迷う方も少なくありません。
ハラスメントや長時間労働、劣悪な作業環境など、安全配慮義務の違反が疑われる場合には、なるべく早い段階で専門機関へ相談することで、適切な対応が受けられ、問題の深刻化を防ぐことができます。
ここでは、主な相談窓口についてわかりやすく解説します。
ハラスメント相談窓口
2020年6月1日に施行された「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」により、大企業にはハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。
また、2022年4月1日からは、中小企業に対してもパワーハラスメント防止措置の実施が義務化され、その一環として相談窓口の設置が求められています。
この相談窓口では、パワハラ、セクハラ、マタハラなどさまざまなハラスメントに関する相談を受け付けています。
相談者は、被害者本人に限らず、同僚や管理職、人事担当者なども対象となるため、幅広い立場から相談をすることができます。
総合労働相談コーナー
厚生労働省が全国に設置している「総合労働相談コーナー」では、無料で労働問題全般の相談に対応しています。
会社の安全配慮義務違反だけでなく、解雇、いじめや嫌がらせ、労働条件など、幅広いトラブルについてのアドバイスを受けることができます。
予約不要で利用でき、必要に応じて労働局や労働基準監督署などの関係機関と連携しながら問題解決の支援を行ってくれます。
労働基準監督署の相談窓口
労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法の遵守を監督する行政機関であり、安全配慮義務違反に対しても対応してくれます。
例えば、長時間労働、過労死、職場での事故などの安全配慮義務の違反があった場合には、労働基準監督署に相談することで、会社に対して調査や立入検査、是正勧告がなされることがあります。
匿名での相談も可能なケースが多いため、会社に相談したことを知られたくないと考えている方でも安心して相談することが可能です。
労災問題に強い弁護士
社内や行政窓口だけでは解決が難しいケースでは、労災問題に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
特に、安全配慮義務違反によって実際に怪我等をしてしまった場合、損害賠償や慰謝料の請求を行うには法的な支援を受けることが必要不可欠です。
弁護士であれば、労災の申請から後遺障害等級認定、損害賠償の交渉や訴訟まで、専門的な知見に基づいて対応することが可能です。
弁護士の支援を受けることで、適正な後遺障害等級認定や賠償額の獲得が見込める可能性が大きく高まります。
最近では、初回無料相談や完全成功報酬制を導入している法律事務所も増えており、費用面でのハードルも下がっています。
「法律のことはよくわからない」「費用が不安」と感じている方でも、ぜひ1度弁護士にご相談ください。
労災問題を弁護士に相談すべき理由については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。
安全配慮義務のよくあるQ&A
安全配慮義務に関する疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
ここでは、特に寄せられることの多いご質問について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

安全配慮義務違反を訴えたいときはどうすればいい?
 安全配慮義務違反で会社を訴えたいと考えている場合は、まず労災問題に強い弁護士へ相談しましょう。
安全配慮義務違反で会社を訴えたいと考えている場合は、まず労災問題に強い弁護士へ相談しましょう。
弁護士に相談することで、訴訟が可能なケースかどうかを法的な観点から判断してもらうことができます。
また、損害賠償や慰謝料を請求する場合に必要な証拠の集め方や手続きの進め方についても、具体的なアドバイスが得られます。
たとえば、長時間労働による過労や、適切な安全対策が取られていなかったことが原因で怪我や病気を負った場合には、安全配慮義務違反に該当する可能性があります。
こうした場合、民事訴訟によって会社の責任を問うことが可能です。
「会社に責任を問いたい」「手続きの進め方がわからない」と思ったら、迷わず弁護士に相談するのが最善の一歩です。

管理職にも安全配慮義務はあるの?
 管理職にも一定の安全配慮義務が求められます。
管理職にも一定の安全配慮義務が求められます。
安全配慮義務は、基本的には使用者(=会社)が従業員に対して負う法的義務です。
ただし、会社は法人格を持つ法律上の存在であり、実際に従業員の管理や指導を担っているのは、代表取締役や取締役、そして現場の管理職(部長や課長など)といった個人です。
そのため、現場で部下を管理・指導する立場にある管理職にも、安全配慮義務の一端を担う役割があると考えられています。
もし、部下が長時間労働をしているのに見て見ぬふりをしたり、体調不良を訴える部下に過剰な業務を与え続けた場合には、管理職として安全配慮義務を怠ったと評価される可能性があります。
実際の裁判でも、「上司が異変に気づいていながら何もしなかった」といった事実が、会社の安全配慮義務違反を認定する材料となっている例があります。
管理職は単に業務を指示するだけでなく、職場の状況を把握し、従業員の心身の健康や安全に配慮した業務管理を行うことが求められます。
会社側としても、管理職への教育や制度整備を通じて、安全配慮義務を適切に果たせる体制を構築することが重要です。
まとめ
安全配慮義務は、会社が従業員に対して必ず果たさなければならない法的な責任です。
これは単なる道徳的な配慮ではなく、労働契約法に明記された義務であり、企業は従業員の命や健康を守る義務を負っています。
これを怠ると法的責任を問われ、損害賠償の対象になる可能性があることはもちろん、刑事罰や行政指導が科される可能性もあります。
例えば、長時間労働が慢性化している、職場でのパワハラが放置されている、適切な健康診断が行われていないといった状況が継続している場合、会社は安全配慮義務を果たしていない可能性があります。
最悪の場合には、労災事故や精神疾患の発症といった深刻な結果を招くおそれもあります。
過去の裁判例では、安全配慮義務違反が認定された場合、会社に対して数百万円から数千万円単位の損害賠償が命じられたケースも多数存在します。
会社にとっても無視できない重要なリスク要因といえます。
他方で、働く側にとっても、こうした問題を自分ひとりで抱え込むのは非常に危険です。
「この会社、大丈夫かな?」と少しでも不安に感じたら、まずは安全配慮義務という観点から問題がないかを確認することが大切です。
安全配慮義務の違反が疑われる場合や、体調を崩した原因が職場環境にあると感じる場合は、早めに労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、法的な観点から現在の状況を整理でき、損害賠償や労災申請など必要な手続きについてアドバイスを受けることができます。
従業員の命や健康、そして人生を守るためにも、「安全配慮義務」という法的概念を正しく理解し、必要な行動を起こすことが重要です。
弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。
オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。