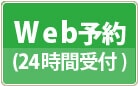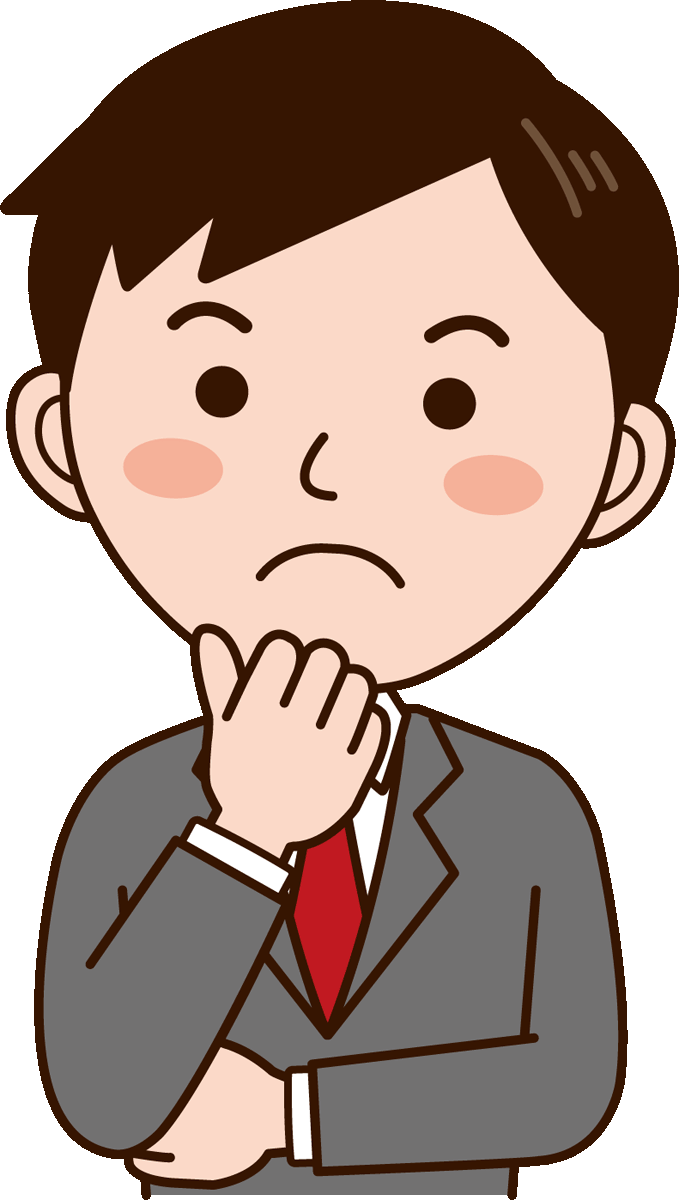預金を持ち出した妻からの生活費の請求に応じなければならない?
事例
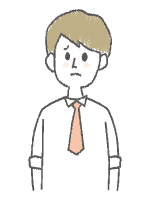 先日、妻が夫婦の預金の一部である500万円を引出して、一方的に家を出ていきました。
先日、妻が夫婦の預金の一部である500万円を引出して、一方的に家を出ていきました。
そのうえで、生活費として、毎月10万円を支払うように求められてしまいました。
500万円も持ち出されたのに、毎月10万円も支払えと言うなんて酷いと思います。
この生活費の支払いの請求に応じなければならないのでしょうか?

 まず、前提として、別居期間中の生活費のことを婚姻費用といいます。これは、民法760条に基づき認められるものです。
まず、前提として、別居期間中の生活費のことを婚姻費用といいます。これは、民法760条に基づき認められるものです。
そして、その適正額は、裁判所が用いる一定の計算式から算出されます。(これをまとめたのが、いわゆる算定表というものです。)
この問題について、婚姻費用の問題に詳しい当事務所の弁護士が解説いたします。
婚姻費用の基本的な考え方
本件では、まず、双方の年収から毎月の本来の適正額を算出するのが出発点です。

仮に、その結果、10万円が適正額だったとしましょう。
その場合、通常、妻から婚姻費用の支払いを求められたら、毎月10万円を支払わなければなりません。支払わない場合は家庭裁判所が審判により、10万円の支払いをあなたに命じることになります。
ところが、本件では、妻が預金の一部である500万円を持ち出しています。そこで、夫としては、「婚姻費用の支払義務があるとしても、持ち出したその500万円から支払ってくれ」と言いたくなります。
この主張は法的に通るのでしょうか。
裁判所の判断事例
結論からいえば、裁判所によって判断が分かれています。
札幌高裁の判断
 例えば、事例のようなケースで、
例えば、事例のようなケースで、
「妻が持ち出した財産の2分の1は、夫が妻に支払うべき婚姻費用として扱うのが当事者間の衡平にかなう。現時点においては、夫に毎月の婚姻費用として妻に支払う必要はない。」
という旨の判断をした例として、札幌高決平成16年5月31日があげられます。
この札幌高裁の考え方によれば、事例においても以下のような判断になりそうです。
妻が持ち出した500万円のうち、財産分与として妻が取得が見込める持分が250万円であるから、夫の持分相当額である250万円は夫が妻に支払うべき婚姻費用として充当できる。
そして、毎月の適正額が10万円であれば、婚姻費用として25ヶ月分を超える未納が生じていなければ、改めて婚姻費用としては請求できない。
別の裁判所の判断
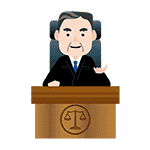 一方で、別の高等裁判所の決定や家庭裁判所の審判の中には
一方で、別の高等裁判所の決定や家庭裁判所の審判の中には
「権利者が持ち出した預金等の夫婦共有財産を生活費に充てることができるとして義務者の婚姻費用分担義務を減免すれば、権利者は財産分与によって取得できるはずの夫婦共有財産を失うことになり、不公平な結果を招くことになるから、婚姻費用分担額の算定にあたって権利者が管理している夫婦共有財産を考慮することは相当ではない。」
としたものもあります。
この考え方によれば、事例においては、以下のような判断をされてしまうでしょう。
妻が持ち出した500万円については、財産分与で考慮・調整すべきであり、婚姻費用としては毎月10万円を妻に支払うべきである。
どちらの判断が妥当かというのが問題になります。
当事務所の弁護士の考え
妻が持ち出した500万円という額が、財産分与の対象として妻が取得しうる額を超えない場合(すなわち共有財産が1000万円以上ある場合)には、夫は別途、月額10万円の婚姻費用を支払わなければならない。
しかし、そうでない場合(すなわち共有財産が1000万円に満たない場合)には、夫は、婚姻費用はまずはその持ち出した分のうち夫側の潜在的持分から充当せよ、と主張できる。
なぜならば、仮に、妻が持ち出した500万円が、明らかに財産分与の対象として妻が取得する額を超えないのであれば、その500万円は潜在的には100%妻の持分といえます。
したがって、本来夫が妻に月々支払うべき婚姻費用を、その500万円から支出しなければならないというのはおかしいといえるのではないでしょうか。

このように、共有財産の持ち出しと婚姻費用分担の問題は、裁判所によっても、考え方が分かれている難しい問題です。
同種のお悩みを持たれている方は、婚姻費用の問題に詳しい当事務所の弁護士にぜひご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?