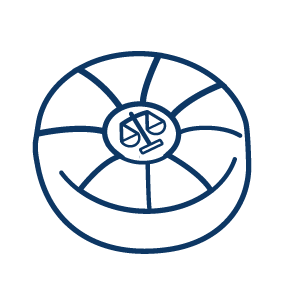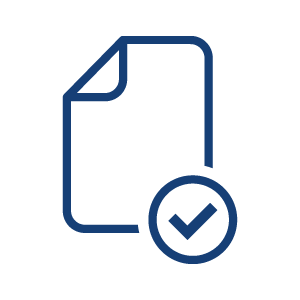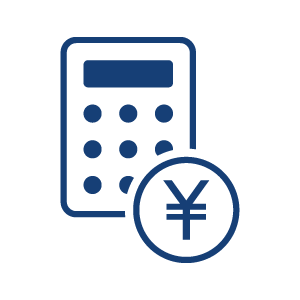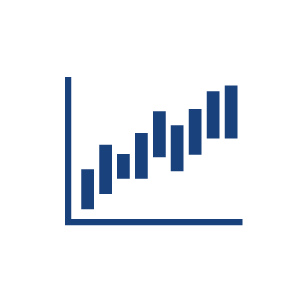遺留分による紛争を防止する方法は?
遺留分の事前放棄や経営承継円滑化法の活用があります。
遺留分の事前放棄について
遺留分は、被相続人の生前に自分の遺留分を放棄することができます。
したがって、後継者以外の相続人(非後継者)に経営者の生前に遺留分を放棄してもらうことによって、遺留分をめぐる紛争や自社株式・事業用資産の分散を防止することができます。
しかし、遺留分を放棄するには、放棄しようとする非後継者が自ら家庭裁判所に申立てを行わなければならず、放棄のメリットがまったくない非後継者の理解を得るのは難しいといえます。
経営承継円滑化法の活用
 このような遺留分の事前放棄の制度の限界を補うため、平成20年に経営承継円滑化法が成立しました。
このような遺留分の事前放棄の制度の限界を補うため、平成20年に経営承継円滑化法が成立しました。
この法律では、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外することができます。
また、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、基礎財産に算入する際の価額を固定することもできます。
すなわち、経営者から後継者に自社株式が生前贈与された場合、何年前になされたものであっても「特別受益」として遺留分算定の基礎財産に加えられますが、その基礎財産に加えられる金額は、贈与された時点ではなく、経営者の相続開始時点での評価によります。
したがって、贈与を受けてから相続開始時までの間に評価額が上昇している場合、上昇後の評価額が贈与を受けた額となって基礎財産に算入されます。
しかも、その評価額の上昇について、贈与を受けた後継者の貢献があったとしても考慮されません。
このため、自社株式の贈与を受けた後、後継者が経営に尽力して会社の価値を上昇させればさせるほど、他の相続人の遺留分の額を増加させるというジレンマに陥ることとなり、会社経営に対する後継者の意欲を削いでしまうおそれがあると指摘されていました。
このような問題点から、経営承継円滑化法では、自社株式の価格固定が認められることとなりました。
なお、価格固定については、後継者を含む現経営者の推定相続人全員の合意を前提としており、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となっていますが、いずれの手続も、メリットを享受する後継者が単独で行うことが可能です。
経営承継円滑化法のくわしい内容は?
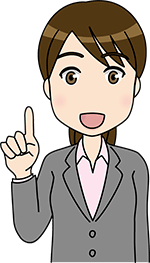 経営承継円滑化法の遺留分の特例を定めるものであり、①遺留分算定の基礎財産から除外する「除外特例」、②遺留分算定の基礎財産に算入する際の価額を固定する「固定特例」があります。
経営承継円滑化法の遺留分の特例を定めるものであり、①遺留分算定の基礎財産から除外する「除外特例」、②遺留分算定の基礎財産に算入する際の価額を固定する「固定特例」があります。
詳細は以下のとおりです。
①除外特例について
この特例は、経営者が後継者に対して生前贈与した自社株式について、遺留分算定の基礎財産に算入しないというものです。
これにより、遺留分減殺の対象から外れますので、相続によって自社株式が分散することを防止することができます。
②固定特例について
この特例は、経営者が後継者に対して生前贈与した自社株式について、遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時点の価額とすることを、あらかじめ合意することができるというものです。
これにより、後継者は、将来の価値上昇による遺留分の増大を心配することなく経営に専念することが可能となります。
なお、合意する株式の価額は、その適正さを裏付けるために「合意の時における相当な価額」であることについて、弁護士、公認会計士若しくは税理士の証明が必要となっています。
特例が適用されるための要件
 対象となる会社
対象となる会社中小企業であって、3年以上継続して事業を行っている非上場会社であること。
 先代経営者
先代経営者特例を受ける先代経営者は、会社の代表者(または過去の代表者)であること。
また、先代経営者の推定相続人のうち、少なくとも一人に対して会社の株式を贈与していなければなりません。
 後継者
後継者後継者は、先代経営者の推定相続人であり、現在において、会社の代表者であること。
また、先代経営者からの贈与等により株式を取得して、会社の議決権の過半数を保有する必要があります。
 合意の必要条件
合意の必要条件以下の条件をクリアしていること。
- 当事者(先代経営者の遺留分を有する推定相続人全員)の合意
- 合意の対象となる株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保することができないこと
- 以下の場合に非後継者がとることができる措置の定めがあること
-
- 後継者が合意対象の株式等を処分した場合
- 先代経営者生存中に後継者が代表者でなくなった場合
-
合意書の記載内容
経営承継円滑化法の特例を利用するためには、その合意について書面を作成することが必要です。
合意書の記載例についてはこちらをごらんください。
手続
この特例に係る合意が効力を生じるには、次の手続を踏む必要があります。
- 合意後、1か月以内に、経済産業大臣の確認を申請すること
- 経済産業大臣の確認を受けてから1か月以内に、家庭裁判所の許可の申立てを行うこと
民法特例のための合意書の作成やその後の手続については、法律的な専門知識が必要となりますので、事業承継に詳しい弁護士によく相談をしましょう。
事業承継についてもっとお知りになりたい方はこちら
|
●事業承継とは |
●事業承継の方法 |
|
●経営や資産を引き継ぐ方法 |
●社長(経営者)が所有する株式について |
|
●遺留分による紛争を防止する方法について |
●事業承継において相続税はどのように計算するのですか? |